はじめに
こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。
前回の記事では、「スマイ伴走」という考え方について解説しました。
スマイ伴走とは「スモールステップ」「マニュアル」「インセンティブ」「伴走」の4つから成り立つもので、
このどれかが欠けると、せっかく元気を取り戻したZ世代社員でも新しいチャレンジになかなか踏み出せません。
詳しくは👇(前回の記事)
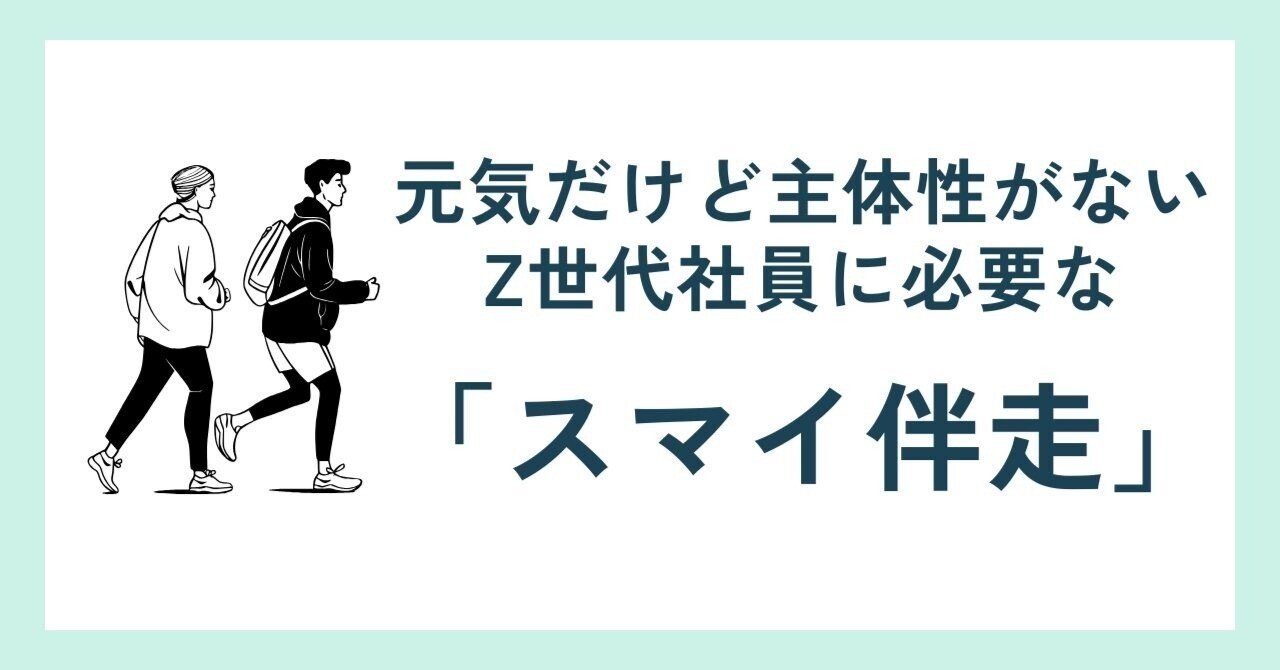
そして、その中でも特に難しくて奥が深いのが「スモールステップ」だ、という話をしました。
今回は、このスモールステップを具体的にどう理解し、現場でどう活かしていくかを(なるべく簡単に)整理していきます。
前提として理解したい2つの欲求と2つのストッパー
具体的なスモールステップの説明に入る前に、人間がもつ2つの欲求と、それを満たそうとするときに働く2つの心理的ストッパーについて触れておきたいと思います。
遠回りなようですが、様々あるスモールステップを体系立てて深く理解するには、ここをまずは押えることが大事です。
(なお、今から説明する2つの欲求と2つのスモールステップは👇の記事のほぼコピペです!)
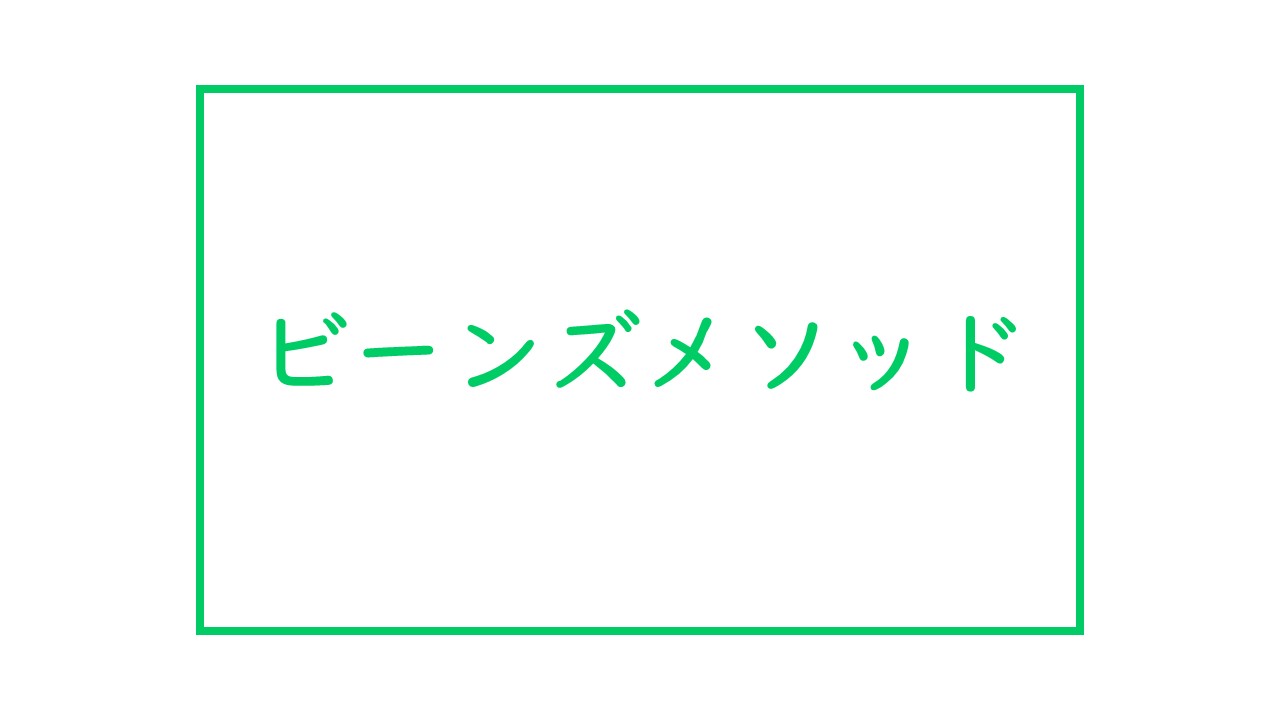
ありのまま欲求とストッパー
「ありのまま欲求」とは、
- ありのままの自分でいたい
- ありのままの自分を丸ごと承認してほしい
という欲求のことです。
ただし、この欲求を最初からのびのびと満たせる人はいません。
なぜなら、「ありのままじゃダメだ」「ありのままでは愛されない」というストッパーが心の中で生じるからです。
※以前の記事(👇)で紹介した概念で説明すれば、これは「自分も他人も道具扱い」しているがゆえに生まれるストッパーです。
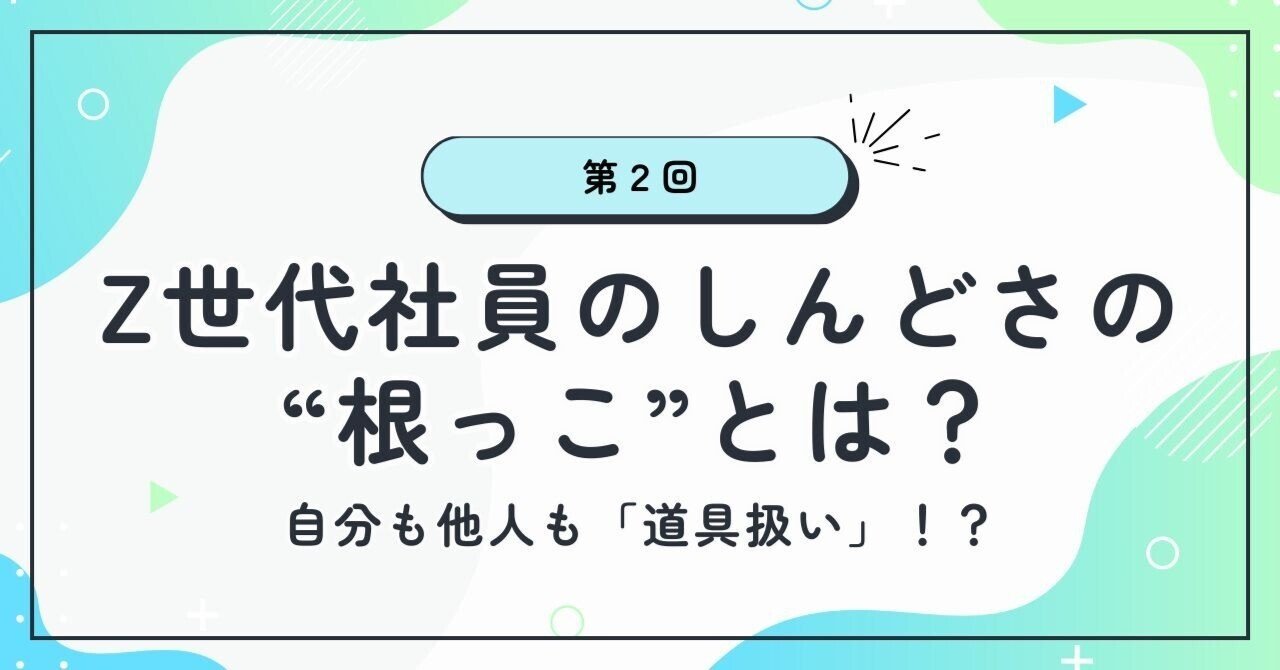
ドライブ欲求とストッパー
もうひとつが「ドライブ欲求」です。
これは「自分でリスクとコストを引き受けて、成功したい」という欲求です。
仕事で成果を出すときも、友達と遊ぶときも、自分で何も決めずリスクも負わない状態だと、どこか味気なくつまらないものになってしまいます。
重要なのは「自分でリスクとコストを引き受ける」という部分です。
人は利益だけでなく、そこに伴う失敗のリスクや時間的・金銭的・体力的なコストを引き受けてこそ、達成感や快感を得られるのです。
例えば、日本で当たり前に使える水道やネット。便利ですが「やったー!最高!」と快感を感じる人はいないでしょう。そこには「自分でコストを引き受けて確保した」というドライブ感がないからです。
一方で、初めての一人暮らしで自分でネット回線を吟味して契約し、快適なネット環境を整えたときには「自分で決めてやり遂げた」というドライブ感を得られます。
しかし、この欲求にもストッパーがあります。
「リスクやコストが怖い」という心のブレーキです。
例えば、起業したいと思っていても、リスクを恐れて踏み出せない人が多いのは、このストッパーのせいですね……
さて……
ここで強調しておきたいのは、スモールステップを設計するときは、以上の2つの欲求に働く2つのストッパーを解除することを目的にするという点です。
スモールステップ解説
では、いよいよスモールステップについてです。
現場で使えるスモールステップは数多くありますが、大きく3つに分けられます。
- ありのまま欲求のストッパーを解除するもの
- ドライブ欲求のストッパーを解除するもの
- そのどちらにも当てはまるもの
具体的には、以下の3つです。
- タテマエ → ホンネ のスモールステップ
- 無責任 → 有責任 のスモールステップ
- 同質 → 異質 のスモールステップ
このうち「タテマエ→ホンネ」は、不登校の10代支援などでよく使いますが、企業の人材育成の現場では「無責任→有責任」の方が重要なので、ここでは詳しくは触れません。
同質 → 異質のスモールステップ
これは文字通り、慣れ親しんだ“同質”の世界から、少しずつ“異質”な世界に移行していくためのスモールステップです。
代表的なのが「無意識→意識」のスモールステップです。
部下が気づかないうちに、挑戦に必要な基本動作を習得させたり、業務を身近に感じてもらうものです。
例1:将来プレゼンを任せたい場合
- 将来の挑戦:お客様の前でプレゼンできるようになる
- 前提となる基本動作:人前で簡潔に説明できること
- 任せ方:
「明日の朝礼で、昨日の会議内容を2分で説明して」
→ 本人は“報告役”のつもりだが、人前でまとめて話す練習になっている。
例2:将来顧客交渉を任せたい場合
- 将来の挑戦:価格交渉や条件調整ができるようになる
- 前提となる基本動作:相手の話を正しく聞き取り、整理する力
- 任せ方:
「今日の打ち合わせ、議事録をまとめて。相手の要望とこちらの回答を2列に整理してね」
→ 本人は“記録作業”だと思っているが、相手の主張を要点でつかむ力が鍛えられる。
その他の例
- 新人研修を任せたいなら、普段の研修をその部下の近くで実施する。
- 将来広報担当にしたいなら、まず既存記事の校閲を担当させて「記事を読むのが当たり前」という状態をつくる。
無責任 → 有責任のスモールステップ
ここでいう「責任」とは、挑戦に伴って支払うリスクとコストのことです。
このタイプのスモールステップには様々な形がありますが、ここでは代表的な2つを紹介します。
1. みんなでやる → 一人でやる
初めての挑戦をいきなり一人に任せるのではなく、まずは複数人で取り組ませる。
とてもシンプルですが、効果的なステップです。
2. 他人事 → 自分事
最近「○○を自分事として捉えてほしい」という言葉をよく耳にします。
社会課題や会社の目標など、いろいろな場面で使われますよね。
もちろん反論はしませんが、強調しすぎて「他人事」が悪いことのようになっていませんか?
実際は、いきなり「自分事」にできる人なんてほとんどいません。
多くの場合、「他人事」から始まり、少しずつ「自分事」になっていくものです。
例えば資料作りなら、最初から本人に作らせるのではなく、上司が作った資料にアドバイスさせる程度から始める。
そのうち「自分でも作りたい」という気持ちが出てきたタイミングで初めて、資料作りを任せる。
コラム:進路指導の現場から
私が塾長を務める「学習支援塾ビーンズ」の10代の進路指導現場でも「いきなり自分事を突きつけない」ことが徹底されています。
- 先輩が進路を選ぶ姿を見学する
- 大学生講師の就活を手伝う
- 面接練習でも、最初は“面接官役”を担当する
こうしたステップを踏んで、最後に本人が「私がやる!」と自発的に手を挙げる。
この流れが自然なチャレンジへの移行なのです。
おわりに
今回は、スモールステップを理解する前提として「2つの欲求と2つのストッパー」を整理し、その上で代表的なスモールステップを紹介しました。
今回はあくまでさわり部分だけでしたので、詳しくは研修・コンサルティングなどでお伝えしていきます。
※「スモールステップ」は本当に奥が深いです……
私以外の人材育成・組織開発の専門家(龍之介さん)が執筆した👇の記事も併せてご覧くださいませ! 違った視点で「スモールステップ」の理解を深めることができます。
(私の記事も参考のひとつにして執筆された記事とのことです…… 龍之介さん、ありがとうございます!)
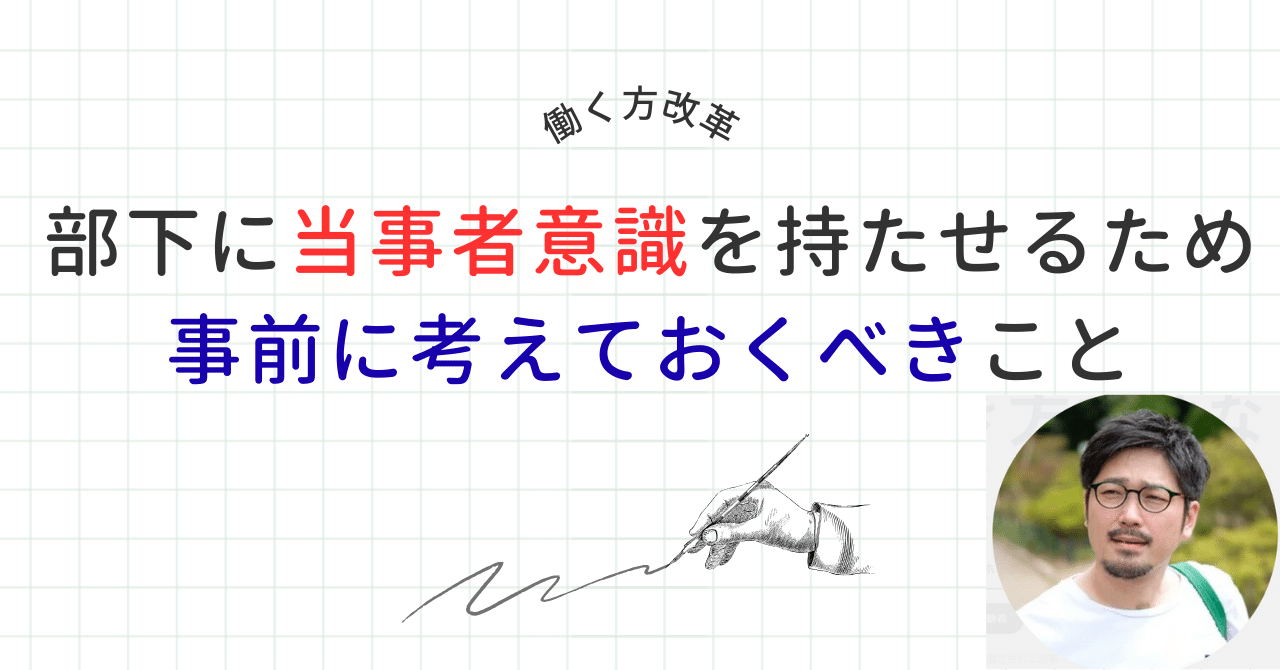
また、読者アンケートにも協力いただけますと幸いです!
(回答時間目安3分)










