具体例から理解したい方はコチラ
はじめに
こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。
長澤啓(Nagasawa kei)
東京大学経済学部卒。1997年生まれ。
大企業・大企業の組合幹部向けの研修(ダイジェスト動画)・コンサルティングで、「Z世代社員の定着と活躍」のコツについてお伝えしている。長澤の取り組みについて詳しくはコチラ。
不登校支援専門塾である「学習支援塾ビーンズ」の塾長/副代表も務める。
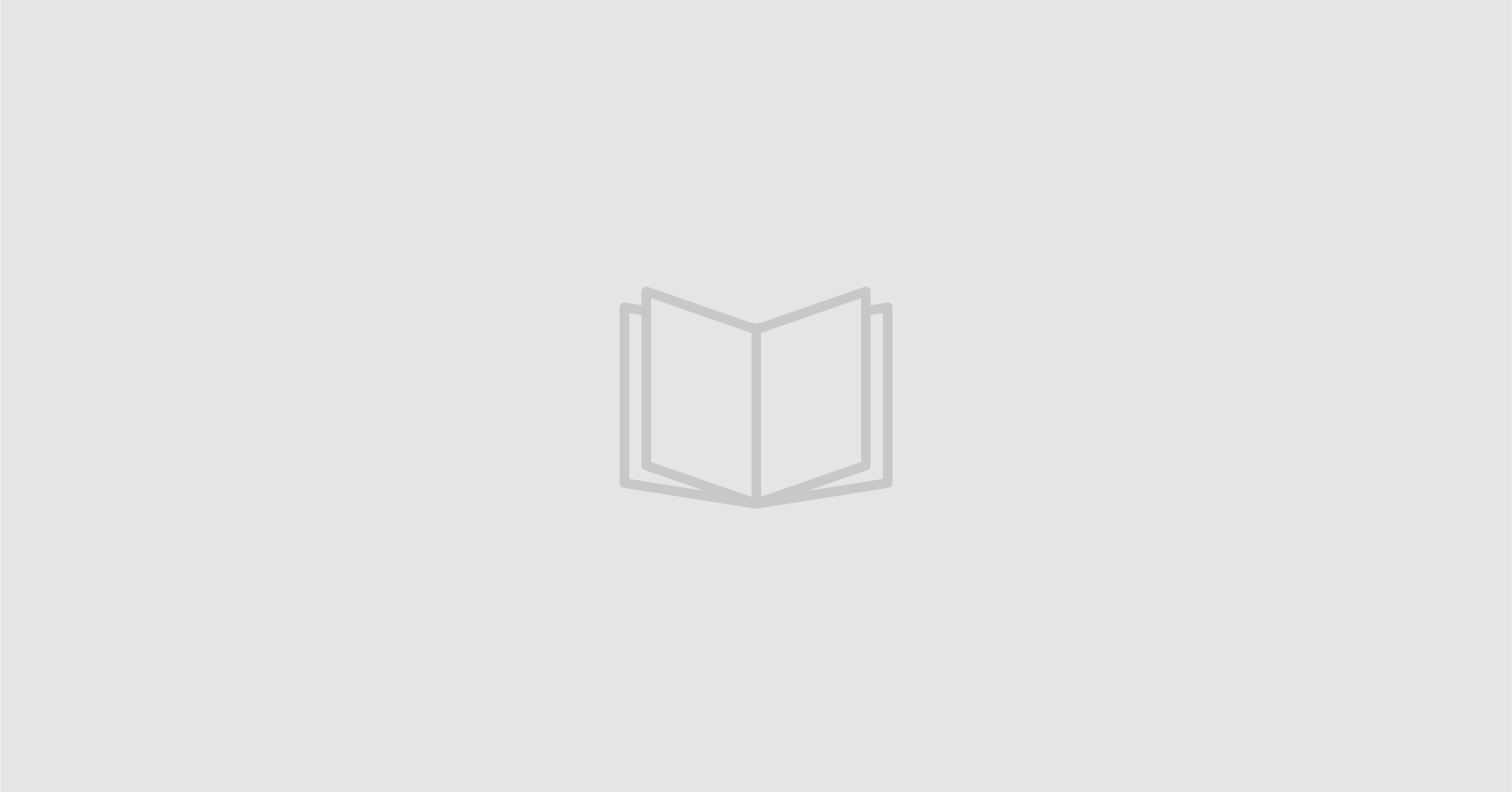
今回からいよいよこのシリーズ(↑)の最終章、
「Z世代社員のしんどさの“原因分析編”」
に入っていきます。
「いや、原因の分析より先に“打ち手”を教えてよ!」
そんな声が聞こえてきそうですね。
たしかに、現場でZ世代と関わっていると「すぐにでも改善したい!」という気持ちになるのは当然です。
でも、本シリーズでテーマにしている「自己閉塞」(詳しくは↓)と呼ばれるしんどさって、ほんっっっとうに根が深い問題なんです。

原因をすっ飛ばして「この施策で解決!」なんて雑な対応をすると、
逆効果になることもあります。
だからこそ、ここは焦らずに、ちょっとずつ本題に入っていきましょう。
「Z世代が悪い」vs「社会が悪い」──どっちも正しいし、どっちも間違ってる
まずは、よくある話から。
Z世代のしんどさを語るとき、
よく出てくるのがこの対立構造。
- 「Z世代は我慢が足りない!根性がない!」
- 「いやいや、悪いのは社会だよ。Z世代は被害者でしかない」
たぶん、この記事を読んでいる人の多くは後者寄りかと思います。
(「いやいや、そもそもZ世代は元気だよ!」という方はまずコチラの記事をご覧ください。「生まれる子どもの数が過去最少なのに、不登校も小中高生の自殺者数も過去最多を更新し続けているんだから、Z世代の心に”何か”が起きているのは間違いない」という結論です)
Z世代の端くれとして言わせてもらえば、
社会のせいにしてくれるのはちょっと嬉しい。
責められないだけで救われる部分もある。
でも…
それだけじゃ、なんだか腑に落ちないんです。
「いや、Z世代自身が自分で墓穴掘ってる部分も確実にあるのでは?」
って思う瞬間があるんですよね。
つまり、問題はもっと複雑。
何か一つの要因が悪いわけではなく、
社会・周りの人・本人の3者が絡み合い、
共犯的に“自己閉塞”を生み出しているんです。

自己閉塞を生む「共犯関係」とは?
たとえば、目の前に「自己閉塞」状態のZ世代社員がいたとします。
彼または彼女はなぜ、自己閉塞に陥ってしまったのか。
その原因は、
ひとことで言えば「社会」「周囲の人」「本人」の三者による共犯関係です。
それぞれの問題が複雑に絡まり合いながら、「自己閉塞」に陥らせてしまっているんです。
このあたりの構造について簡単に図解したものがありますので、先に紹介しておきますね。
今回と次回は下図を念頭に解説していきたいと思います。

では、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
【1】社会の問題──Z世代だけに強まる“生きづらさ”
社会の側には、少なくとも以下の4つの変化が大きく影響しています。

衰退する経済
まずシンプルに、お金の不安が世代を問わず広がっています。
「今は何とかなってるけど、この先どうなるんだろう?」
「子どもに十分な教育を受けさせられるだろうか?」
こういった将来不安は、親世代の余裕を削り、その影響はZ世代にも波及します。
抑圧的な教育システム
画一的な詰込み教育は減ったかもしれませんが、今は今で別の抑圧が生まれています。
それが、「探究学習」「アントレプレナー教育」などの“主体性推し”です。
もちろん、理念は素晴らしい。
優れた教育者がある程度元気な生徒に探究的な学習の機会を届けることには大賛成です。
でも……
私が塾長を務める不登校支援専門の塾、学習支援塾ビーンズの生徒からはこんな声が上がってきます。

「好きなことがない自分は価値がないの?」
「主体性がないとダメなの?」
まさに、
「主体性がないと“道具”としての価値がないとみなされ、捨てられるかもしれない……」
という恐怖心ですね……
(自己閉塞という状況を理解するうえで必ず理解すべき“道具的世界観”については下記の記事をご覧ください。)

孤独なライフスタイル
昔は仕事も娯楽もそれ以外の暮らしも「誰かと一緒」じゃないとできませんでした。
しかし、今は違います。
技術の進化により、向こう1か月くらいは他人と深く関わらなくても、暮らしていける時代になりました。
ですから、「嫌われるリスクを背負ってまで他人と深く関わる」という短期的なインセンティブがなくなったのです。
結果として、本気でぶつかり合う人間関係が減り、「嫌われないこと」が最優先になってしまいます。
他人を助けない国民性
データを見る限り、日本人は他者への親切行動が国際的に少ないらしいです。

困っても「誰も助けてくれないかも」という不安感。
これがベースにあるからこそ、失敗や弱音がますます言えなくなるんですよね。
【2】周りの人の問題
さて、「周りの人の問題」について見ていきたいと思います。
最初に、大前提としてお伝えしたいことが2つあります。
前提①:3つの関係領域とは?
まず1つ目の前提は、子どもや若者が育っていく上で重要な「3つの関係領域」について。
それは、
- 「親との関係」
- 「大人との関係」
- 「同世代との関係」
の3つです。
この3つの関係が、どんな風に形成されるか、あるいは傷つくかが、Z世代の自己形成や心の土台に大きく関わってきます。
ちなみに「大人との関係」とは、親以外の大人、たとえば学校の先生、塾の先生、近所のおっちゃんおばちゃん、バイト先の店長などを指します。
※学習支援塾ビーンズが不登校などに悩む10代の対応法として練り上げたビーンズメソッドの4階構造で言えば、1階から3階にあたる部分ですね。
前提②:トラウマとは?

そしてもう1つの前提は、「トラウマ」について。
私は、トラウマという言葉を少し広めにとらえています。
「今の自分の行動を制限してしまうような、嫌な思い出」
それが、私の定義するトラウマです。
つまり、たとえ嫌な思い出があったとしても、それが今の自分に特に影響を与えていなければ、それは単なる「過去の嫌な記憶」にすぎません。
でも、その記憶が今もなお、
「あの時みたいに傷ついたら怖い」
「もう二度とあんな目にあいたくない」
と、自分の行動を萎縮させたり、挑戦を避けるようにしてしまうなら、それはもう立派なトラウマです。
3つの関係領域の相互補完
ここからが本題です。
実は、1つの関係領域で嫌な思い出があっても、他の2つの関係領域でうまく回復できれば、トラウマ化しにくいのです。
たとえば、親との関係でしんどい思いをしても、
- 学校の先生が優しく寄り添ってくれた
- 同級生と遊んで気持ちをリセットできた
といった体験があれば、その傷は自然に癒やされ、やがて本人の中で「嫌だったけど、まあそういうこともあるよね」と消化されていきます。
でも、今はその「補完」が非常に難しい時代になっている。
なぜか?
それは、先ほど述べた「社会の問題」の進展により、この3つの関係領域すべてが同時に劣化しつつあるからです。
まず親との関係。
経済の衰退や、孤独なライフスタイルの進展によって、多くの親たちは心身の余裕を失っています。
ある親は、生活費を稼ぐために必死で働いて、子どもとじっくり向き合う時間も気力もないかもしれません。
逆に、経済的にそこそこ余裕がある親でも、
「今はいいけど、日本の将来は不安」
と感じて、子どもに強い成果を求めてしまう。
「もっと頑張りなさい」「将来困らないように、いま努力しておかないと」
と、知らず知らずのうちに教育虐待のような関わり方になってしまうこともあります。
つまり、親自身が社会の圧力に押されるなかで、「安全基地」としての機能を果たしづらくなっているのです。
次に、「親以外の大人」との関係。
これも社会の構造変化によって、かなり弱くなってきています。
かつては、地域や親戚、学校などで、子どもが接する「親じゃない大人」がたくさんいました。
でも今は、地域コミュニティや血縁コミュニティの崩壊が進み、そういった大人と出会う機会自体が減っています。
さらに、学校の先生たちも多忙で心の余裕がなく、
昔のように生徒一人ひとりの心のケアをするのは難しい状況です。
つまり、子どもや若者が親以外の大人に「逃げ込む」チャンスが、著しく減ってしまっているのです。
最後に、同世代との関係。
同世代は「深くつながる仲間」ではなく、「比較される対象」になってしまっています。
そして、そもそも同世代とつながる場も減っています。
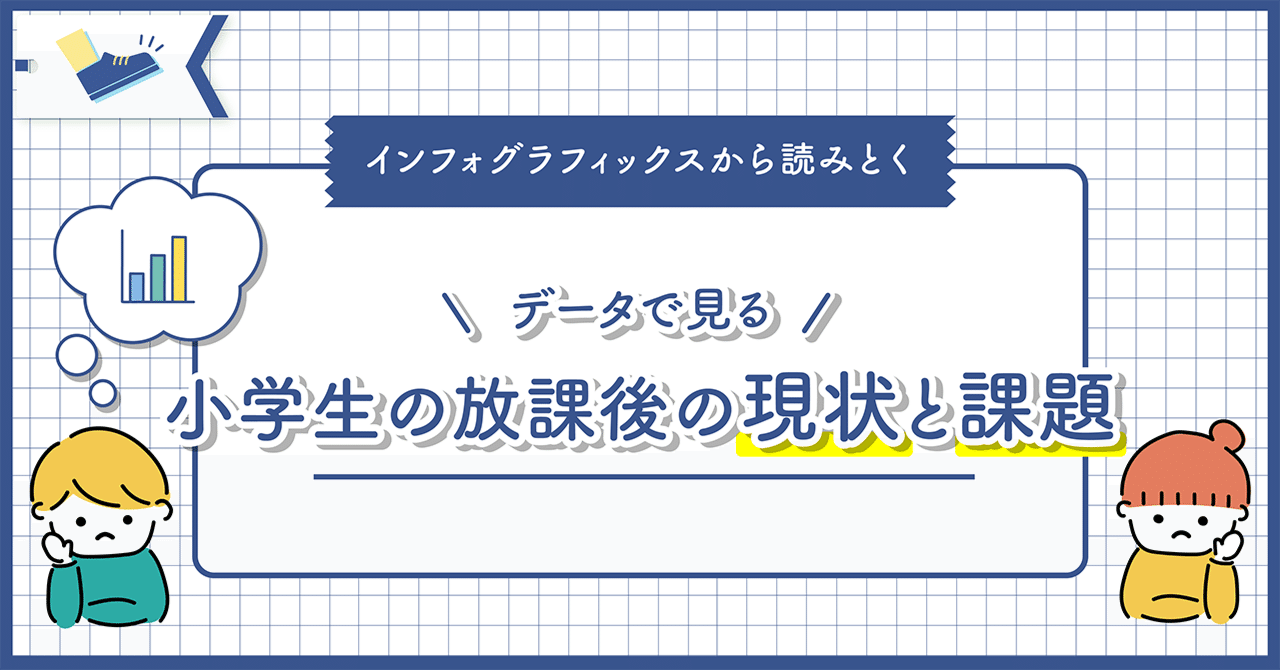
つまり、同世代との関係もまた「安心できる逃げ場」にはなりづらくなっているのです。
とある元気そうな就活生の「親トラウマ」
ぱっと見元気そうなとある就活生に伴走したときのことです。
ESも書ききり、あとは出すだけ!って状態になった途端に、その就活生の手が止まり、泣き出してしまいました。
話を聞くと……
「小学生のとき、私の塾の成績に少しだけ落ち込んでいる様子の母親の顔を思い出して辛い……」
と言うのです。
さらに深く聞いてみると、両親ともにおおらかな人で、何の問題もないように見えました。
ただ、その就活生にとって、自分をどこまでも伴走してくれる親以外の大人や本音で語れる同世代がいなかったので、「母親が少し落ち込んだ」というちょっとしたことがトラウマ化してしまったわけです。
(ちなみに、その就活生は某プライム上場企業で元気にやってます)
かすり傷が致命傷になる時代
こうして3つの関係領域が同時に劣化していくと、どうなるか。
——それは、「かすり傷が致命傷になる」という事態です。
たとえば、
- 自分のちょっとした発言を友達にスルーされた
- 親が自分の行動でちょっと悲しそうな顔をした
- 担任の先生に一度だけ厳しく怒られた
こういった
「上の世代からすればなんてことのない経験」が、一部のZ世代にとっては強烈なトラウマになってしまう。
なぜなら、それを回復できる関係領域(居場所)が、どこにもないからです。
誰にも頼れず、話す相手もおらず、心の中でぐるぐると傷を深めていく。
結果として、その傷はやがて「自己閉塞」へとつながってしまうのです。
さいごに(次回予告)
今回お伝えしたのは、
- 社会の構造的変化
- 周囲との関係性の希薄化
- それによるトラウマの蓄積
といった背景から、Z世代の「自己閉塞」がどうやって生まれるかという“構造”の話でした。
大事なのは、どこか一か所を責めるのではなく、
「この3つが共犯的に絡み合っている」と理解すること。
そして、次回はいよいよ最後のピース、「本人の問題」について解説します。
下図の下半分ですね……

- 社会や周囲の影響を受けて、Z世代の“内面”には何が起きているのか?
- そして、それがどう社会全体に循環していくのか?
Z世代社員の「しんどさの根っこ」シリーズ、最終回もぜひご覧ください。
👇次回(シリーズ最終回)の記事

また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、こちらの問い合わせフォームからお声がけくださいませ。












-──-Z世代社員のしんどさの根っことは?-300x157.jpg)