こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。
長澤啓(Nagasawa kei)
東京大学経済学部卒。1997年生まれ。
大企業・大企業の組合幹部向けの研修(ダイジェスト動画)・コンサルティングで、「Z世代社員の定着と活躍」のコツについてお伝えしている。長澤の取り組みについて詳しくはコチラ。
不登校支援専門塾である「学習支援塾ビーンズ」の塾長/副代表も務める。
今までの記事で、デリケートなZ世代の行動を
の4つに分類して解説してきました。
今回のテーマは「使用価値向上」です。
いよいよ最後です……!
私自身、この使用価値向上に分類される行動をとることが多く、書きながら「いや~~ 自分もそうだわ~~」となってます(笑)
さて……
「うちの会社のZ世代社員はやる気があって元気ですよ!」
と自信満々におっしゃる上司世代の方は多いのですが、それは本当なのでしょうか???
実は、Z世代社員の側が、
やる気がある感じを見せなきゃ、上司たちから「使えない道具」として捨てられてしまう……
という恐怖心から、巧妙に演技をしていたり、しんどさを抱えながら頑張っていることも多いように感じます。
また……
研修などで、多くの上司世代の方から
うちのZ世代社員、やたらとマニュアルを欲しがるんですが……
と相談されることがあります。
今日は、このあたりについて深掘りして解説していければと思います。
↓前回記事

↓↓本シリーズの記事のまとめ↓↓
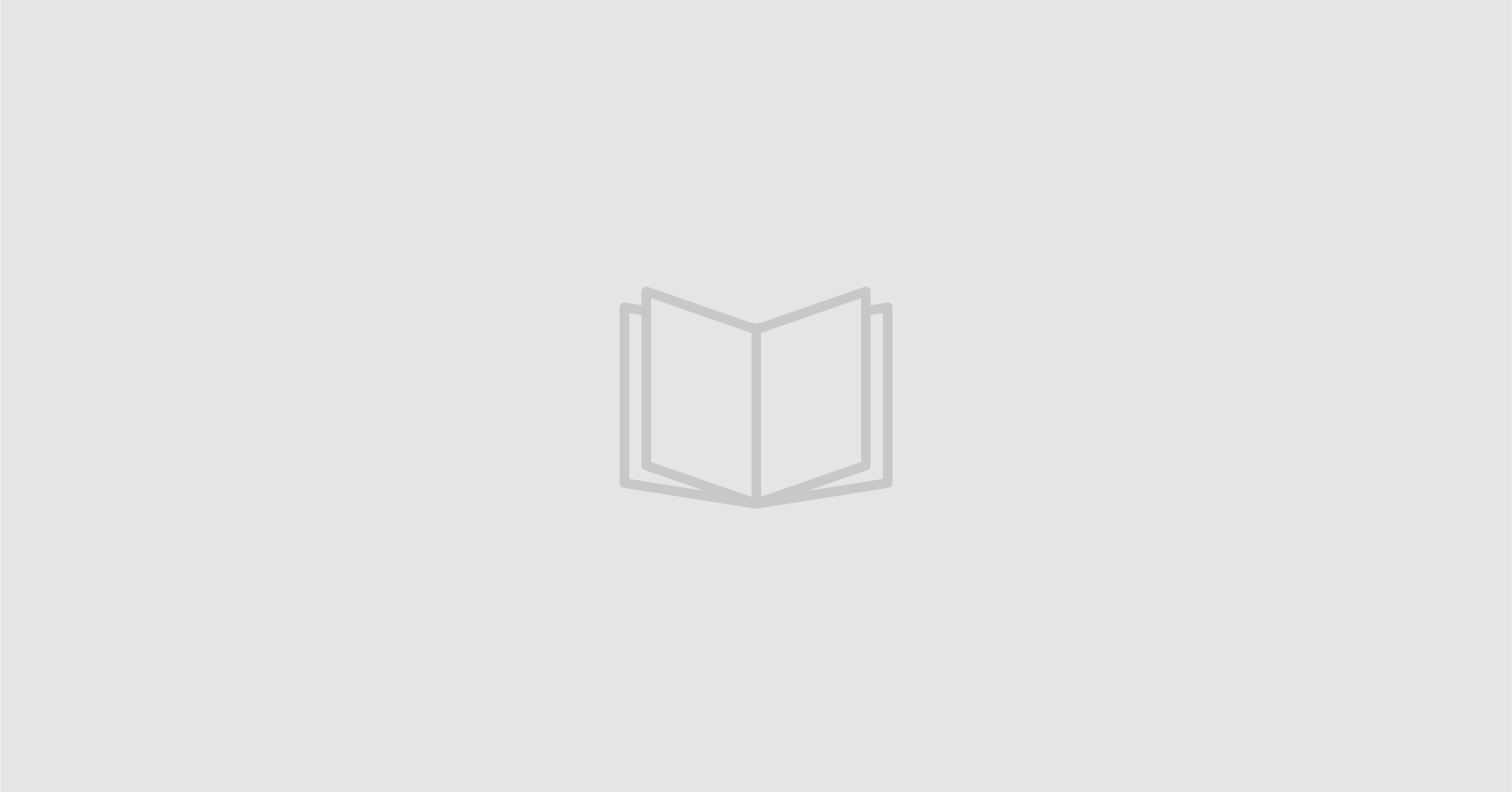
↓併せて読んでいただきたい記事

使用価値向上

使用サイクル志向かつ被使用者志向の行動類型は「使用価値向上」です。
自分の道具としての使用価値を高める、
もしくは、
使用者が期待する便益の量を調整することによって、
使用サイクルを周回し続け、関係解消を避けようとする行動です。

もちろん、使用サイクルをどれだけ周回しても関係解消への恐怖はなくなりませんから、この行動をいくらやっても心は満たされません。
使用価値向上にカテゴライズされる行動は以下のように分類できます。
評価獲得
使用価値向上の代表例ともいうべき行動です。
自身の使用価値を上げるために、
能力・ステータス・実績の獲得に躍起になります。
私が塾長を務める不登校支援専門の塾、学習支援塾ビーンズの生徒の一部が、小学生から高校生まで「学歴」にこだわる状態もまさにこれにあたります。
怖いのが、一定の暗記力と要領、そして体力ゆえに努力を継続できてしまい、
知力ゆえに効率的に成果を出してしまう場合もあるので、
社会的には本当に評価されてしまう場合が多いということです。
成果を出したところで本人の心は満たされないので、痛みを抱えたままです(東大生に多いですね)。
評価獲得行動にはおおまかに2つのパターンがあります。
1つ目は、ストイック至上主義です。
これは、学習支援塾ビーンズのサイトでも紹介していますが……
ストイックであることそのものを目的にしてしまう状態のことです。
- 楽しく仕事をする
- 楽しく学ぶ
といった、普通の感覚からすると、「え、めっちゃいいじゃん!」ということに対しても……
「こんなに楽しいことが自分の成長に寄与するわけがない」
「(本来苦しいことをやるべき)仕事でこんな楽しい時間を過ごしてはいけない」
と苦しんでしまいます。
2つ目は、スキル・ステータス・実績に頼るパターンです。
「学歴・人脈や、資格などの分かりやすいスキル・実績を獲得すれば、使用サイクルを無限に周回できて関係解消に陥らないかも!」
という期待(誤解ですが)のもと、努力します。
さらに、評価獲得行動に陥ったZ世代社員の特徴として、
「自分と同じレベルであるはずの誰かへの苦手意識」
が挙げられます。特に、同世代への苦手意識が顕著です。
評価獲得行動に陥っているZ世代社員は、
他人との比較(競争)を無意識的にでもかなり気にします(※)。
そのため、自分と比べられる可能性が高い同世代(同期・同僚)への苦手意識が顕著になるのです。
そのため、自分よりも劣っていると判断した同世代は見下して、
一歩踏み込んで関わろうとはしません。
だからといって、自分よりも優れていると判断した同世代(自分よりも大活躍している同世代など)と切磋琢磨し合う深い関係を築こうとするかというと、そういうわけでもありません。
なぜならば、それはそれで自分の劣等性を直視することになるのではないかという恐怖心があるからです。
※
道具は他の道具と比較可能で取り換え可能です。なぜならば、道具から得られる便益(使用価値)は比較可能であり、同等もしくはそれ以上の便益をもたらすものと取り換えても問題ないからです。
規範依存
別名「いい子ちゃん行動」です。
先述の評価獲得行動と重なる部分も大きいです。
道具である自分が集団から関係解消されないために、
「所属する集団の規範を機械的に墨守し、自分の行動を規範に最適化すれば良い」
という動機で行われる行動です。
規範に従ってさえいれば、関係解消される(捨てられる)リスクを最小化できるという考えが根底にあります。
また、少しでも規範から逸脱した他人を強く攻撃してしまうこともあります。
先日、私が実施している研修に参加いただいた某大企業の上司世代の方から面白い(?)話を聞きました。
人事部によって社内の新卒新入社員向けの集まりが開催されたそうです。
新入社員同士の親睦を深めようという趣旨の集まりなので、お菓子も準備されてあったのですが……
誰もお菓子に手を伸ばさなかったそうです。
何かがおかしいと思って参加者の新入社員の一人に深く話を聞いたところ、
「会社の集まりでお菓子を食べるのはあり得ない。自分がお菓子を食べるところを上司たちの誰かが見ていて、自分への評価を下げるかもしれない。第一、お菓子を食べたときの音が怖くてとても食べる気になれない」
と、真顔で答えられたそうです。
そもそも、お菓子は会社側が用意しているものなのですが……
これはどちらかというと、前回紹介した「埋没」に近い行動なのですが、規範依存とも考えられるので、本記事のコラムで紹介させてもらいました。どうでもいいですが、「開けるときのプシュって音が怖いので、炭酸系飲料も怖い」ということも教えてもらったそうです。
ちなみに、学習支援塾ビーンズの生徒の例を挙げると……
自身も不登校傾向が強いにも関わらず、
他の生徒に対して
「不登校なんてとんでもない! 許せん!」
と感情的になってしまうことがあります。
この捻じれた現象も、この規範依存による行動だと考えられています。
正解依存
規範依存の派生形といってもいいかもしれません。
「正解」にすがることで自分の使用価値を確実なものとしようとする行動です。
未知のことをやる際に、確立された完璧な方法論にすがろうとするのです。
「完璧な」とは、自分が創意工夫や思考する隙が一切ないという意味です。
自分の創意工夫や思考がわずかでも入ってしまうと、
失敗した場合に自分の使用価値の低さが露呈します。
しかし、自分の創意工夫や思考が入っていない「正解」をトレースした結果として失敗しても、
「完璧であるはずの正解が完璧でなかったのが悪い」
とすることができますから、自分が関係解消されるリスクが減るのです。
一部のZ世代社員が、詳細で緻密なマニュアルを求めてしまうのはこれが理由です。
言うまでもありませんが、仕事において文字通り完璧な正解など存在しません。
また失敗を正解のせいにしても「完璧な正解を完璧じゃないと見抜けなかった自分が悪い」という考え方も成り立ちますから、きついままです。
ですから、完璧な正解を求める行為は常に失敗する運命にあります……
そして、ここからさらに重要なのは、
仮に存在しえない完璧な正解が存在したとしても、やはりきつい状況であることに変わりないということです。
存在しえない完璧な正解が存在し、
それを完璧にトレースして行動し、
何事かに成功したとしてもそれは自分の功ではなく、完璧な正解の功であるということになります。
自分は何も創意工夫したり思考したり選択したりしているわけではないのですから。
そして自己閉塞人は自身の使用価値(便益)を上げるための獲得に躍起になるという傾向からすれば、
自分は何も創意工夫したり思考したり選択したりしていない中での成功は喜ぶことができません。
別の人間が運用しても変わらずに成果を上げられるということですから、他人との取り換え可能性が高まり、関係解消されるリスクがむしろ高まります。
つまり、完璧な正解があったとしても、幸せになることはないのです。(※)
※
なお、この構造に気づいた自己閉塞人は、逆に「正解が誰からも全く提示されていない状態で成果を上げる」ということに過剰にこだわる評価獲得行動に走ります。これが発展すると、「完全に誰の力も借りずに自分一人だけで成果を上げるんだ!」と躍起になります。いわば、前回の記事で紹介した「一人親方」の状態に憧れるのです。しかし、誰の力も借りない状態では大きな成果を上げることは難しく、道具としての価値も向上しません。なお、成果を出している一人親方ほど、一人親方であるからこそ他人からの助けを大事にしていることは言うまでもありません。
誰もが知っている都内の超一流大学に通い、大きなテニスサークルの代表も務めるほどコミュ力抜群な就活生の相談にのったときの話です。
彼は、「大企業だと、完璧なマニュアルがあって、絶対に仕事で失敗しないはず。だから大企業に行きたい。ちなみに、自分だけの才能を生かした仕事がしたい。」と言うのです……
まさに、正解依存と前回紹介した行動のどちらにも当てはまる発言でしたので、やたら記憶に残っており、コラムで紹介せずにはいられませんでした(笑)
過度な謝罪
自分が相手が期待したような便益を提供できなかったことを先に謝罪することで、「廃棄」しないように懇願することが目的です。
少しのミスや、相手に迷惑をかけたかもしれないという事実に傷つき、
過度に謝罪します。
この”少し”の程度について、一例だけあげると、
「自分の悩みを相談し、相手に時間をつかってもらった」
というようなことですら相手に迷惑をかけ、謝罪しなければならない事案であるとみなしてしまうこともあります。
また”謝罪”についても、相手のことを思って、誠心誠意で謝る……
というよりは、自分を守るために無意味な反復ともとれるほど、過剰に謝罪するのが特徴です。
(そのため、謝罪される側からするとむしろ不快に感じることが多い)
期待値調整
自分を道具として使用しようとしている(と少なくとも主観の中で感じている)人が期待する使用価値(便益)の量を調整することによって、
使用サイクルを周回し続け、関係解消を避けようとする行動にまさに分類されます。
そもそも相手が自分に過剰な使用価値を期待しないようにする行動です。
過剰に自分の能力や実績を低く表現することで、廃棄や切り捨てられる可能性を下げることを狙います。
さいごに(次回予告)
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
前回の記事に、
「それにしてもなんでこうなったのか、原因が気になってきました。」
というコメントをいただきました。
ありがとうございます! よくぞコメントしていただきました!!!
次回の記事(↓)では、Z世代社員(をはじめとする令和の子ども・若者)の自己閉塞性が高まっている理由について解説していきます。

- 社会(経済・技術・教育・国民文化 など)
- 周りの人(親・親以外の大人・同世代)
- 本人
の3つのレイヤーに分けて解説しますので、お楽しみに!
※
「現状と原因の分析は置いといて、打ち手を教えてほしい」という方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、現状と原因をしっかり理解しないと大した打ち手は実行できません。
人体の構造を理解しないまま手術のテクニックを学んでも意味がないのと一緒です。
ですから、現状分析・原因分析にもうしばらくお付き合いくださいませ。
また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、こちらの問い合わせフォームからお声がけくださいませ。











-──-Z世代社員のしんどさの根っことは?-300x157.jpg)