2025年8月2日、学習支援塾ビーンズにて、第一回「全世代に感情力を育む会」が開催されました。
その中で、NPO法人全世代の代表理事 尾身茂先生とビーンズのインターン生である大学生とがクロストークを行いました。
テーマは「現代の若者が直面するコミュニケーションの壁や人間関係の課題」。
尾身先生が語る内容は、若者たちが抱える心の機微を鋭く捉えつつ、課題を乗り越えるための具体的なヒントと、未来への示唆に満ちたものでした。
本記事では、その学びの核心の部分を、皆さんと共有したいと思います!
現代の若者たちが抱える「コミュニケーションの壁」
尾身先生と大学生たちとの最初の話題は、現代の若者たちがコミュニケーションにおいて抱えている特有の課題についてでした。
「意見の否定」=「自己の存在否定」?

最初に大学生たちから提示された課題は…
「自分の意見を否定されると、意見そのものと自分自身とを切り離して考えられない…」
「自分の意見を否定されると、まるで自分の人格そのものを否定されたかのように捉えてしまいがち…」
というもの。
つまり、彼らが感じているのは「意見の否定=自己の存在否定」につながってしまうということです。
この課題に対し尾身先生は…
「意見の否定=自己の存在否定」という考えは、他者からの共感や承認を求める心理の裏返しでもあるのではないか
と指摘されました。
そして「共感や承認を強く求めるというのは、若者特有のことではなく、特別なことでもない」と 語ります。
意見が言えない・悩みが打ち明けられない・深い自己をさらけ出せない

次に大学生たちから提示された課題は、より根深いものでした。それは…
「親しい間柄であっても、悩みや弱みといった深い自己をさらけ出すことへの抵抗感が強い」
「その結果、他者へ意見表明や、他者との深い関わりを避けてしまう」
というもの。
さらに、
「基本、自分以外の他者は敵同士もしくは競争相手。よくて比較の対象」
「たまたま利害が一致したタイミングで仲間になっているに過ぎない」
※このあたりの心理構造については、コチラのnote記事で解説しています。
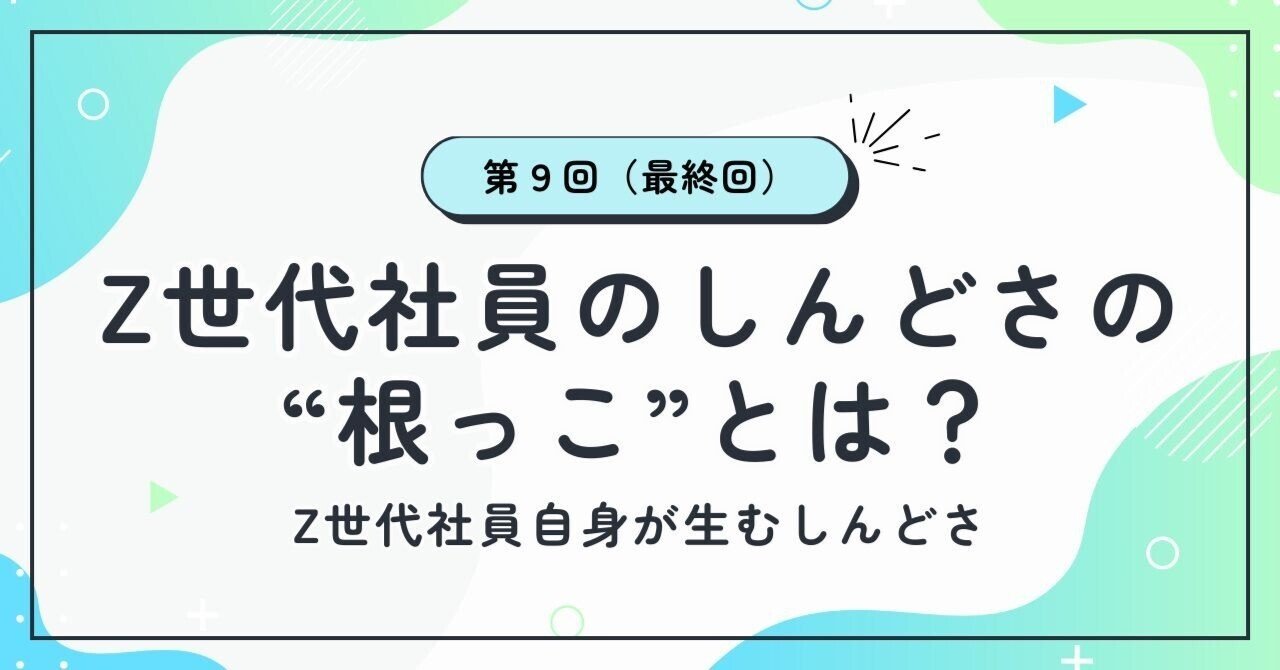
といった、一部の若者たちの中にあるシビアな人間観・世界観が語られました。

こうした若者たちの声を聞いた尾身先生は
 尾身茂先生
尾身茂先生「このようなシビアな人間観や世界観を持っている若い人達がいることは、頭では分っていたが…実際にその心情を直接聞いてみると、これは本質的な社会課題だと実感した。」
と語りました。
そして、一部の若者たちの間にこれほどシビアな人間観・世界観が生まれている背景として、現代の若者たちの傾向として以下の要素が原因になっているのではないか? と問いかけをされました。
● 仲間と本気でぶつかり合うような経験が不足していること
● 仲間とぶつかり合うことがないので、議論できる仲間も得づらくなっていること
● 議論できる場がないので、集団で何か大きな挑戦をする機会が生まれにくいこと
● さらに失敗を恐れることで、挑戦を避けてしまう傾向がより強くなっていること
そして尾身先生は「(上記であげた)こういった要素について、実感はありますか?」と問いかけ、大学生がそれぞれの意見を伝えました。
「不完全さ」を受け入れる人間理解と他者との関わり


続けて、尾身先生からは、大学生から提示された課題、若者たちのシビアな人間観・世界観を乗り 越えるには、まず「人間とは何か」という根源的な問いに向き合う必要があるのではないだろうか…という 提案がありました。
尾身先生が提示されたのは、以下の視点です。
● 人間は本質的に不完全な存在である。例えば、生まれた環境や経済状況など、自分では選べない要因に人生が大きく規定されるという現実がある 。完璧な人間などどこにもいない。
● 私たちにとって論理や合理性だけではなく自分の感情も重要であり、私たちは自分の感情に とって心地よい状態を求める存在である… このことは年齢を問わず人々に共通することだ
人生は「お互いさま」:自分と他者を客観視する視点


尾身先生は続けます。
「自分も相手も”自分では選べない要因に人生を大きく規定された不完全な”存在であること…その点で私たちは “お互いさま”だ。そのことを理解し、それを前提として人間関係を結ぶとよいのではないだろうか…」
「私たちは互いに不完全であり、かつ他人の気持ちを100%理解することも不可能である…よって、おのずと他人 とは意見が食い違っていく。このことを私たちは受け入れていく必要があるのではないか。」
さらに、
「他人は自分のことを常に考えていることはない。他人は他人にとっての課題や人生を考えている。」
「(そもそも)他人は、自分の人生の責任をとってくれるわけでもなく。責任のとりようもない。」
「だからこそ、他人の評価だけにとらわれ、それに一喜一憂する必要はない。」
「他人は自分が思うほど自分のことを気にしておらず、その評価に過剰に囚われる必要はない」
…という言葉は、大学生たちに深い気づきを与えたように思います。
人生の主体性と「新しい物語」の創造へ
失敗も含めて「人間的成長」に


尾身先生は



「人間の成長のためには、成功も失敗も含めた、多様な経験を積むことが重要ではないだろうか?」
と、大学生たちに問いかけます。
具体的には…
● 仲間と本気で意見交換をすること
● 忖度のないホンネの付き合いをして、お互いの気持ちをよく知ること
● 思い切り身体を動かして、(ちょっと)ケガをすること
心身ともに何かにぶつかることでしか得られない「感覚」があり、
その「感覚」によって、本当の喜びや怒り、自分の限界、そして本当に好きなこと(得手)が見えてくるのだ と、尾身先生は語ります。
若者の特権:今こそ「新しい物語」を創造する時
尾身先生は、人生を主体的に生きることと、未来を創るための提言をされました。
● 人生は自分自身のものであり、他人は責任を取ってはくれない…。
だから、他人の評価を絶対視はせず、 自分の人生をどう生きたいかを深く考える時間をとる。
● 人生では、学力や偏差値、IQといったもの以外、人間の感情の成熟度、すなわち“感情力”が重要になる。
● 他人の評価に過度に依拠せず、自分の人生をどう生きたいかを深く考える。
そして、本当の意味での”自分本位”さを手に入れる。
● 人間にとって他の人と一緒にいる時間、仲間と仲良くする時間も大切である。
だが、本当の意味での自分本位さを手に入れるためには、社会の価値観や世間の常識から一時離れ、自分と向き合う時間も重要。
● 自分と向き合う際は、自分中心の視点やSNSからの情報だけでなく、時代を超えて今に伝わる哲学や歴史などに関する書籍など
…つまり自己を超越した視点も取り入れ、「自分の考えを絶対視せず、自分が正しいかどうか」を疑うこと。
そして「自分は、人生で何を求めているか」と自問する時間をとってみることをお勧めする。
こういった内的な対話こそが、孤立感を遠ざけて生きていくコツなのではないか。
…とお話しいただきました。
得手に帆を揚げよ


さらに尾身先生は続けます。
人間はパンだけで生きるのではなく、夢や思想、物語によって生きる存在である。好きなこと、得意なこと(得手) を見つけ、その方向に進む「得手に帆を揚げる」生き方が重要。
人生に困難はつきものだが、夢は人生の困難を乗り越える力を与えてくれる。
確かに現在、社会は流動化している。
一方で、社会が流動化するということは、若者にとって大きなチャンスが存在することも意味しないか。
現代に生きる若者の特権とは、流動化していく社会の中で試行錯誤をしながら…、
皆が納得できる今の世の中にふさわしい「新しい物語」を創造し得ることにある。
自分を絶対視せずに自分を相対化し、一方で「みんなそれぞれ」という相対主義にも留まらず…
他人との議論を通じて「世の中全体のために何ができるか」を考え…
自分のために努力するともに、社会にも貢献する。
そうすることで生きる意味を見出すことができるのではないだろうか。
この言葉で、この日のクロストークは締めくくられました。
今回のクロストークは、ビーンズの大学生たちにとって、自らの人生を深く見つめ直す貴重な機会となりま した。
クロストークに参加して…
大学生からのコメント
尾身先生とのクロストークでは、自身の”ままならない”感情を先生に受け止めていただきました。
そして、尾身先生と話すことによって、自分の理想と現状の課題、その差分を直視することができました。
私の大学生活での課題とはなにか。
それは自身の夢や悩みを語ったり、相手の夢や悩みを聞いたりするコミュニケーションは発生していないことです。
言い換えると、他者との関係が浅いままで終始していることが課題であると考えています。
「大学では、浅い関係の知り合いしかいない」
「大学で、夢や悩みを共有できる仲間はいない」
…このような悩みを抱えているのは、私一人だけではないと思っています。


私は「なぜ他者との関係が浅いままで終わってしまうのか?」と長らく自問自答してきました。
そして、今回のクロストークで尾身先生のお話し、そして様々なエピソードを伺う中で、尾身先生には自分とは違う人生の一つの土台があると感じました。
それは「仲間」の存在です。
尾身先生のエピソードには、
仲間と楽しいことを真剣にやる。
大変なことでも仲間と乗り越える。
しんどい状態になった仲間を見捨てない。
という軸があると、私は感じました。
そして、私は現在の過半数の大学生にとって、これらのことはとてもとても難しい…と考えます。
それはなぜか。
私を含む今の大学生たちは(多かれ少なかれ)コロナ禍の影響を受けています。
また同時にインターネットの発展、社会構造の変化が急激に進みました。
それらを原因として、私達の世代は青春経験が圧倒的に足りていないと感じるのです。
言い換えると、
令和の大学生には、他者と一緒に何かに挑戦する経験、他者とぶつかり合う経験が不足している!
と思うのです。
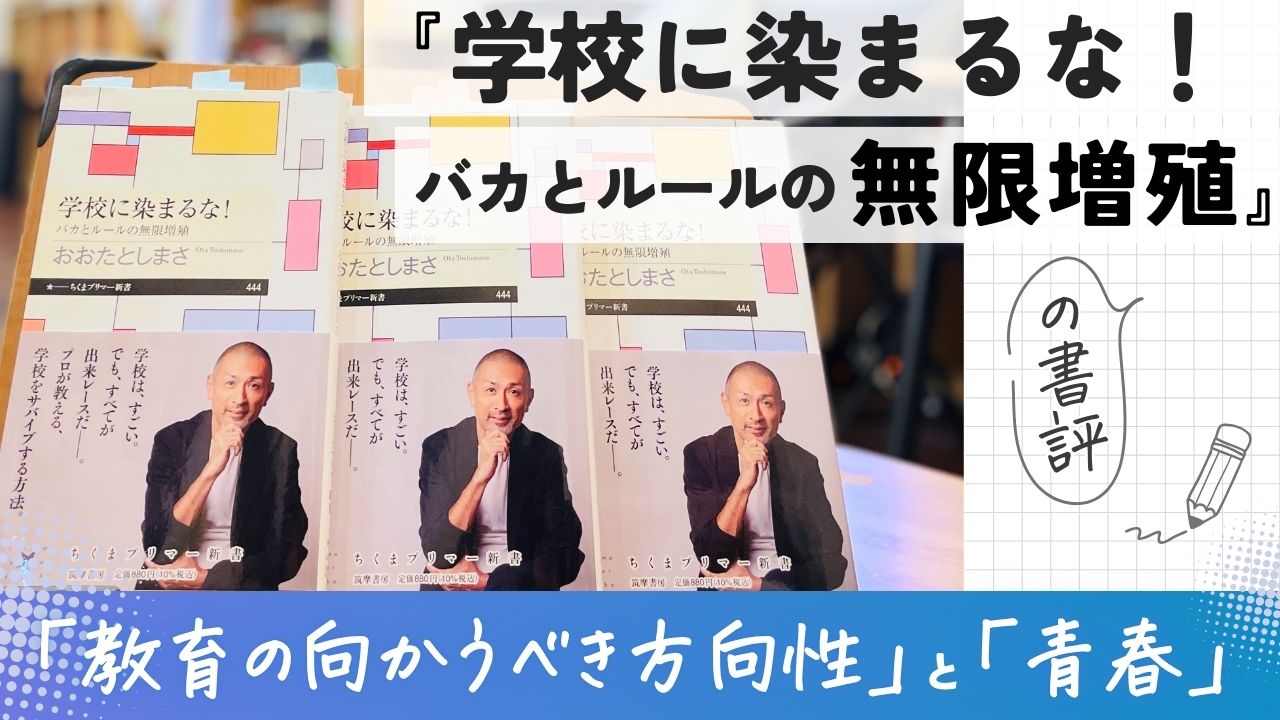
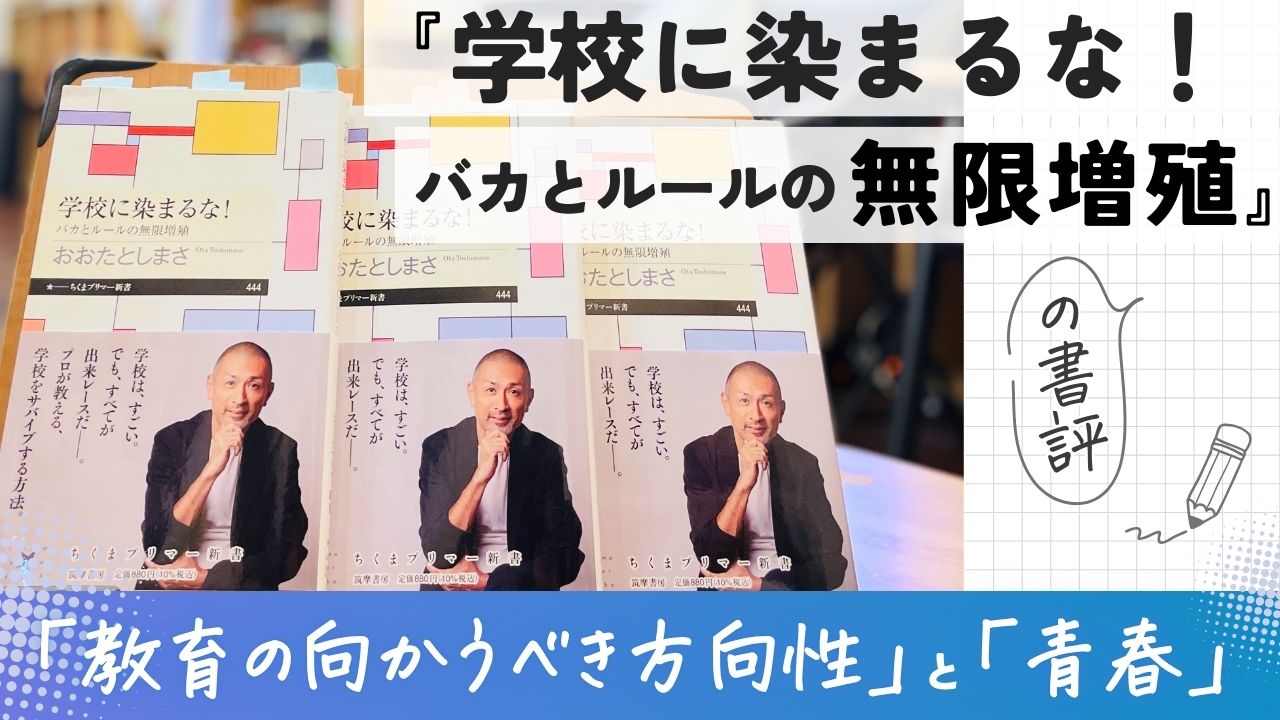
「他者と一緒に何かに挑戦する経験、他者とぶつかり合う経験」の不足。
これが私や他の大学生が他者との関係を浅く終わらせてしまう原因であると思っています。
自分の場合は運よく学習支援塾ビーンズのインターンを見つけ、その環境に飛び込むことで…
自分の悩みをただただ聞いてくれ、自分の”ままならない”感情を受け止めてくれる…
自分の将来への夢の言語化を助けてくれ、時に真剣にアドバイスをくれる…
そんな仲間たちと出会うことができました。
そして、尾身先生に自分の意見を聞いていただける機会もいただきました。
励ましの言葉もいただきました。
もちろん自分が努力した部分もあります。
が、運や偶然の側面は全く否定できません。
自分の努力だけではどうにもならなかったのです…
だからこそ、尾身先生から受け取ったメッセージ、そしてチャンスを他の人にも渡していき、自分だけでなく周りを巻き込む成長の循環を作っていきたい。…と強く思います。
長澤のコメント
学習支援塾ビーンズ塾長の長澤です。


今回のクロストークで一番印象に残ったのは、やはり学生たちが想像以上に“本音”を語ってくれたことです。
正直、尾身先生ほどの方――コロナ禍では毎日のようにニュースに登場していた「ビッグネーム」――を前に、大学生たちがここまで率直に悩みや心情を吐き出すとは思っていませんでした。
萎縮してしまっても当然な場面なのに、学生たちが等身大で自分を語れたのは驚きであり、同時にとても希望を感じました。
もちろん、この奇跡のような現象の背景には、尾身先生の「偉ぶらない空気感」が大きく作用していたのだと思います。
大きな実績とそこから生まれた経験を持ちながらも、威圧感や上下関係を感じさせず…
むしろフラットに「若者を大応援したい!」という気持ちを全身全霊で示してくださいました。
その雰囲気があったからこそ、学生たちは安心して本音を語り、議論が深まったのでしょう。
さて……
ここで尾身先生が示してくださったのは、「挑戦すべき理想」だったと思います。
「他人からの視線や評価を一旦脇に置いて、自分自身と向き合うこと。」
「そして仲間と本気でぶつかり合いながら成長していくこと。」
という理想です。
もちろん、大学生たちにとっての現実では、
「他人の目を気にせず内省に集中する」ことも……
「仲間と忌憚なくぶつかる」ことも……
難しい状況があります。※
※このあたりについては、下記のシリーズ記事で紹介しています。
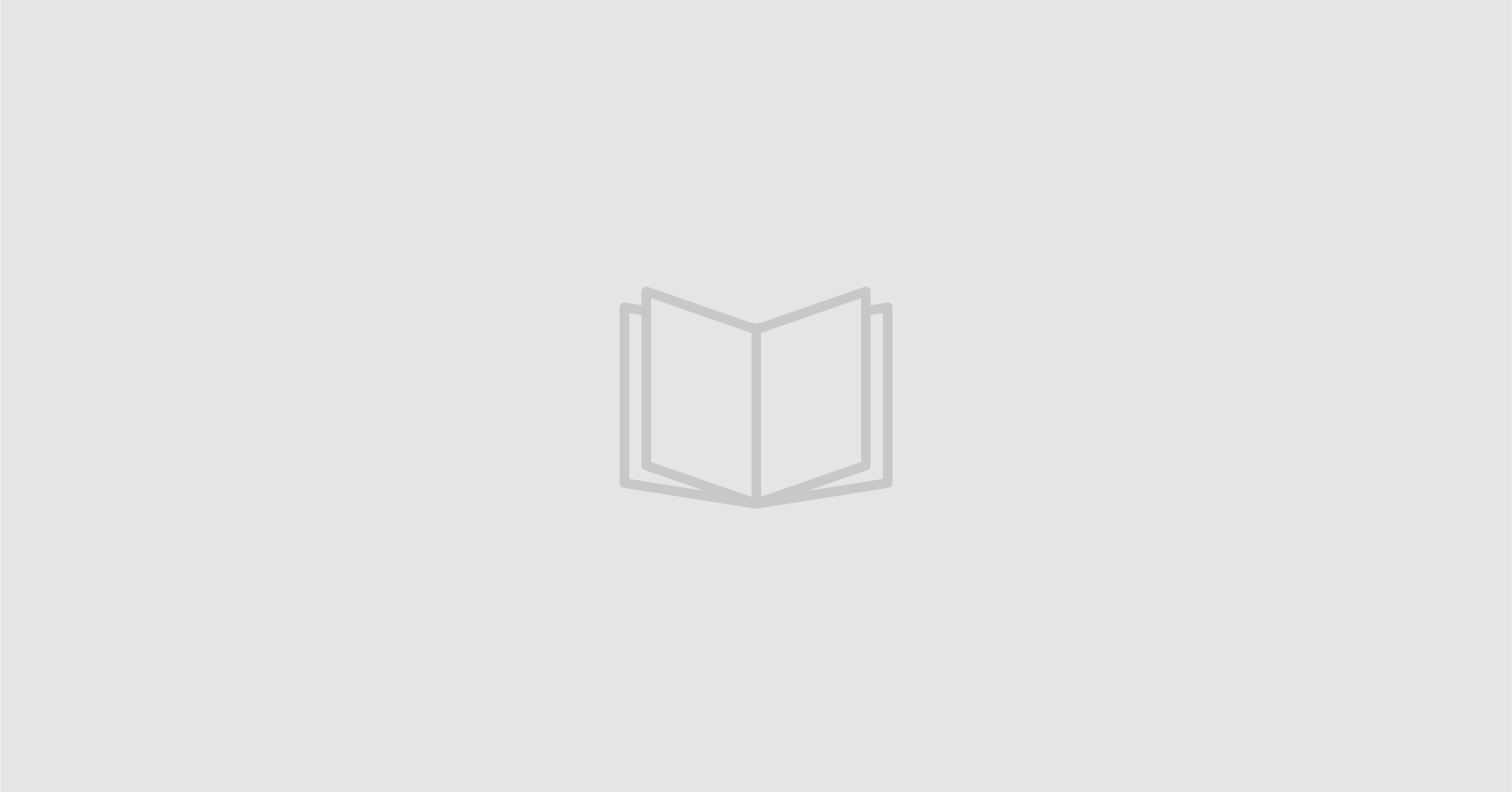
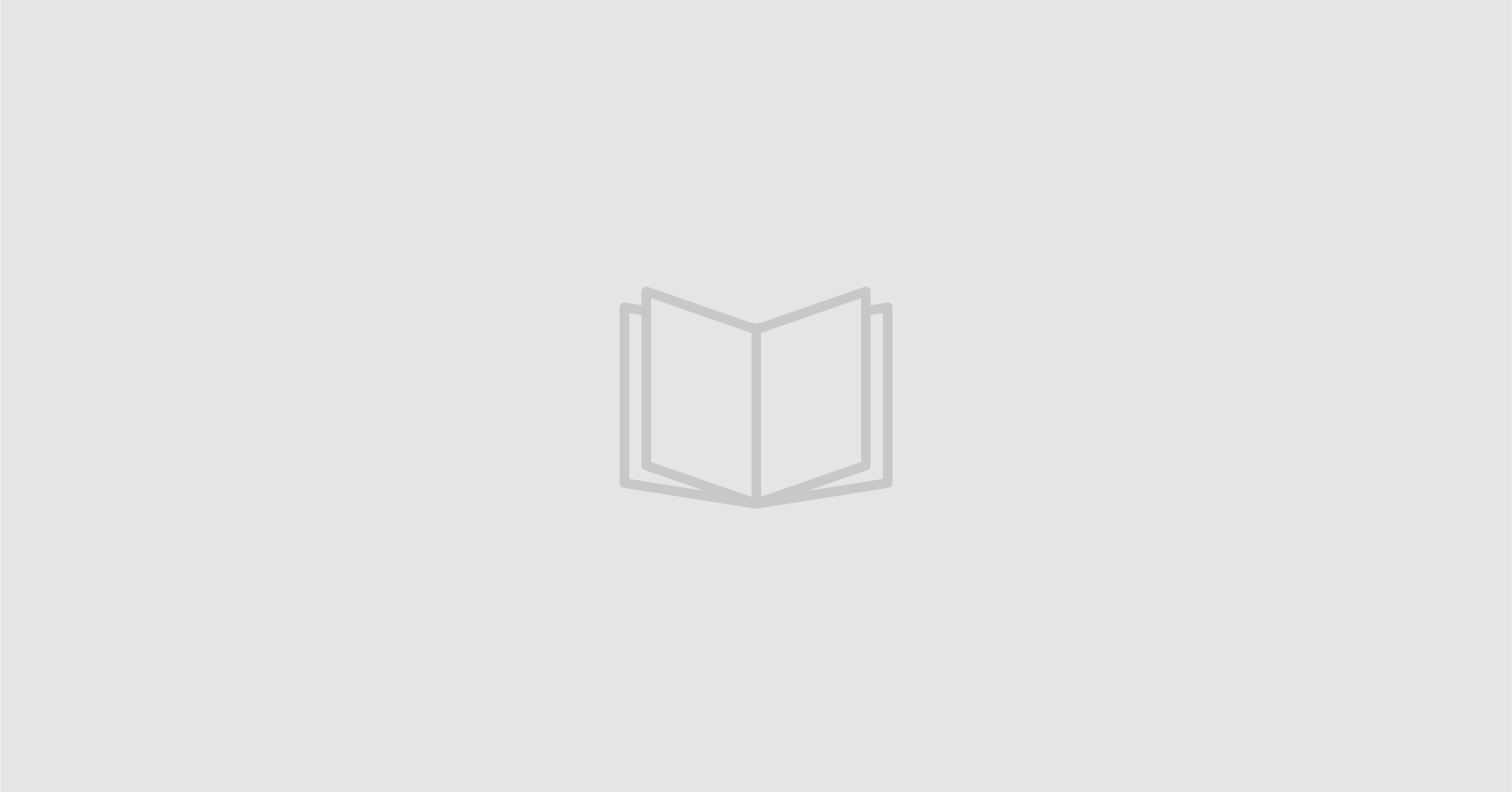
しかし、尾身先生が示してくれた理想は、遠いもののままにしておくこともいけない。と強く思います。
遠い理想であっても……
理想に向かうための方法を探求し、
理想にたどり着くスモールステップを作り上げ、
社会に広めていく…
それが私たちの責務であるという思いを新たにしました。










-──-Z世代社員のしんどさの根っことは?-300x157.jpg)
