具体例から理解したい方はコチラ
はじめに
前回の記事(↓)では、Z世代社員の多くが陥っている「自己閉塞」という課題について解説しました。

↓↓本シリーズの記事のnoteまとめ↓↓
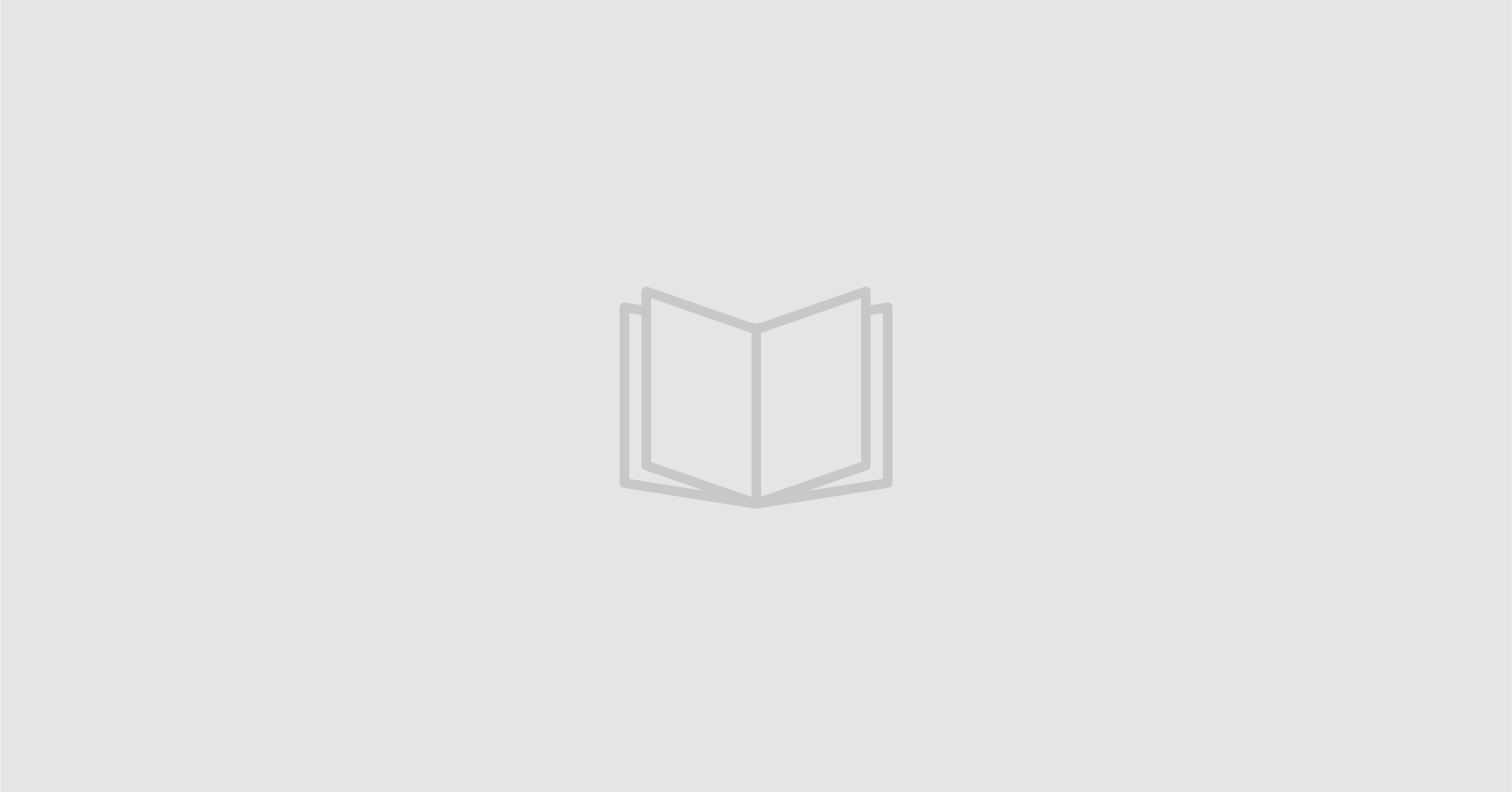
自己閉塞に陥っている人、すなわち「自己閉塞人」は、
自分が嫌いであると同時に、
環境(他者・組織・社会)にも強い苦手意識を抱えているという特徴を持っています。
……と、ここまでが前回のおさらいなのですが、
言い忘れていた大事なことがひとつあります。
それは、
たとえば──
- 昨日まで元気そうに振舞っていたのに、突然パワーダウンしてしまう(予期せぬタイミングで潰れる)
- やる気があるような発言をしていたのに、実際はあまり動かない(発言と行動が一致しない)
- 完璧なマニュアルを求めるが、それは現実には存在しないものだったりする
これらの「一見ちぐはぐな言動」には、実はある深い世界観が関係しています。
今回はその「自己閉塞人の内側にある世界観」について解説していきます。
この世界観が理解できれば、Z世代社員の「不可解な行動」や「読みづらい反応」に、一定の法則性があることが見えてくるかもしれません。
この法則性をしっかりと理解し、実は組織にとってなくてはならない「デリケートなZ世代社員」を育成していきましょう!

長澤啓(Nagasawa kei)
東京大学経済学部卒。1997年生まれ。
大企業・大企業の組合幹部向けの研修(ダイジェスト動画)・コンサルティングで、「Z世代社員の定着と活躍」のコツについてお伝えしている。長澤の取り組みについて詳しくはコチラ。
不登校支援専門塾である「学習支援塾ビーンズ」の塾長/副代表も務める。
自己閉塞人が苦しむ「道具的世界観」
自己閉塞に陥っているZ世代社員の多くが抱えている世界観。それは、簡単に言うと──
「自分も他人も”道具”として見てしまう」
というものです。
にわかには理解しがたいかもしれませんが、安心してください。
順を追って解説していきます。
本来、人間は道具ではありません。
でも、自己閉塞に陥っている人たちは、自分自身や他者を過度に「機能」や「役割」として捉え、道具のように扱ってしまうことで、苦しんでいるのです。
「道具」とは何か?
ここから少し哲学的な話になりますが、「道具」とはそもそもどういうものでしょうか?

道具とは、以下のような関係性のフローで扱われる存在です:
自分の役に立ちそうなモノを探します。役に立ちそうにないモノは最初から目に入りません(=認識外)。
「これなら使えるかも」と予測して当てにします。見込みがなければスルーします。
都合よく使えるように加工します。無理なら切り捨てます。
実際に使って目的を達成。用済みになったら捨てます。
うまくいったらまた期待して、2〜4のプロセスを繰り返します。このサイクルを「使用サイクル」と呼びます。
この一連のプロセスから外れた対象は、「関係外」となります。
特に、いったん期待されたあとに切り捨てられるケースを「関係解消」と呼びます。
道具的世界観の具体例(1)「箸がない!」
たとえば、キャンプに来たけど箸を忘れてしまったとしましょう。
すると、こういうことがおきます。
「この石はダメだな」「葉っぱも無理」→ 認識外
このプロセスでは、枝は「箸という機能を果たすモノ」として扱われています。
道具的世界観の具体例(2)謝罪メール
今度は、物理的なモノではなく「言葉」に目を向けてみましょう。
たとえば、上司に謝罪メールを送るとき。
- 探索:「どんな言葉なら失礼じゃないか?」→ 「やっほ〜」は即・認識外
- 期待:「誠に申し訳ございません」ならいけそう
- 制御:文中にうまく組み込む
- 消費:送信
- 廃棄:メールが届いた時点で、その言葉の役割は終了
言葉もまた「使われるモノ=道具」として扱われているのです。
道具的世界観の具体例(3)人を「道具扱い」する
さて、ここで本題に戻ります。
人間も、この「道具の扱い方」によって接することができるのでしょうか?
実はできます。たとえば──「優秀な人材の選抜プロセス」はまさにその典型です。
売店の店員などはそもそも視界に入らない(認識外)
もし、研修でダメだと分かったら選抜候補から外す
さらに高いノルマを課す
そして、うまくいけばまた期待し、使用サイクルを繰り返す──。
極端な例ですが、人間もこのように「期待→制御→消費→廃棄」のサイクルで扱われることがあります。
ビジネスの場では、人を道具的に扱うことが「効率的」になる場面も少なくありません。
ただし、それが行きすぎると、関わるすべての人がしんどくなってしまいます。
自分や他人を「過剰に」道具扱いすると?
ここが一番大切な話です。
特に、いったん期待された上で切り捨てられる「関係解消」は大きな痛みを伴います。
だからこそ、自己閉塞人たちは「関係解消されないように」行動を最適化しようとします。
しかしそのような行動は「(本当は人間だけど)道具である“自分が”関係解消されないようにする(捨てられないようにする)」というセルフィッシュなモチベーションがベースにあります。
だからこそ、環境(他者・組織・社会)からますます愛されなくなってしまうのです……
そして、お気づきかもしれませんが、このような行動こそが「自己閉塞行動」なのです。
期待されないようにする行動
- 認識外に行こうとする:会議中に自分の意見を出さない
- 褒められるのを避ける(↓):褒められれば期待される→プレッシャー→関係解消のリスク
先生、どうか皆の前でほめないで下さい: いい子症候群の若者たち
道具として価値を高め続ける行動(使用サイクル周回)
- 積極的周回:恐怖ベースで社内MVPを狙う、肩書にこだわる、恐怖ベースの成長意欲
- 消極的周回:完璧なマニュアルにこだわる、失敗しないことを最優先する
共通するのは、「捨てられたくない」というネガティブなモチベーションです。
ちなみに、筆者の出身大学である東京大学には積極的周回タイプの人が多い印象です(というか今の私もそうです…苦笑)。
まあ、在学中に自分の自己閉塞性との折り合いをなんとか見つけてなんだかんだで幸せになっていくものなのですが、たまにそれができずに入院するような人もいます……
ただ、東大に入るような人ってそもそもの体力や地頭がずば抜けている人が多いので、自己閉塞に苦しんでいてもなんだかんだで結果を出し続け、傷つきながらも走り続けることができる人が多い印象ですね。
余談が過ぎました……(笑)
10代の不登校の子どもたちとの共通点
この話、実はZ世代社員に限った話ではありません。
私が学生時代から関わってきた不登校の10代の子どもたちにも、まったく同じような傾向が見られます。
- 傷つけられたくないから、最初から人と関わらない(認識外行動)
- 「普通」「学歴」「勉強」にこだわり、コンプレックスを埋め合わせしようとする(使用サイクル周回)
- そしてさらにしんどくなる
Z世代社員と不登校の子どもたちの間には、非常に似た心理構造があるのです。
このあたりの話は、不登校支援に特化したサイトで詳しく発信しています。

興味のある方は、そちらも読んでみてください。特に↓の記事は参考になるかもしれません…
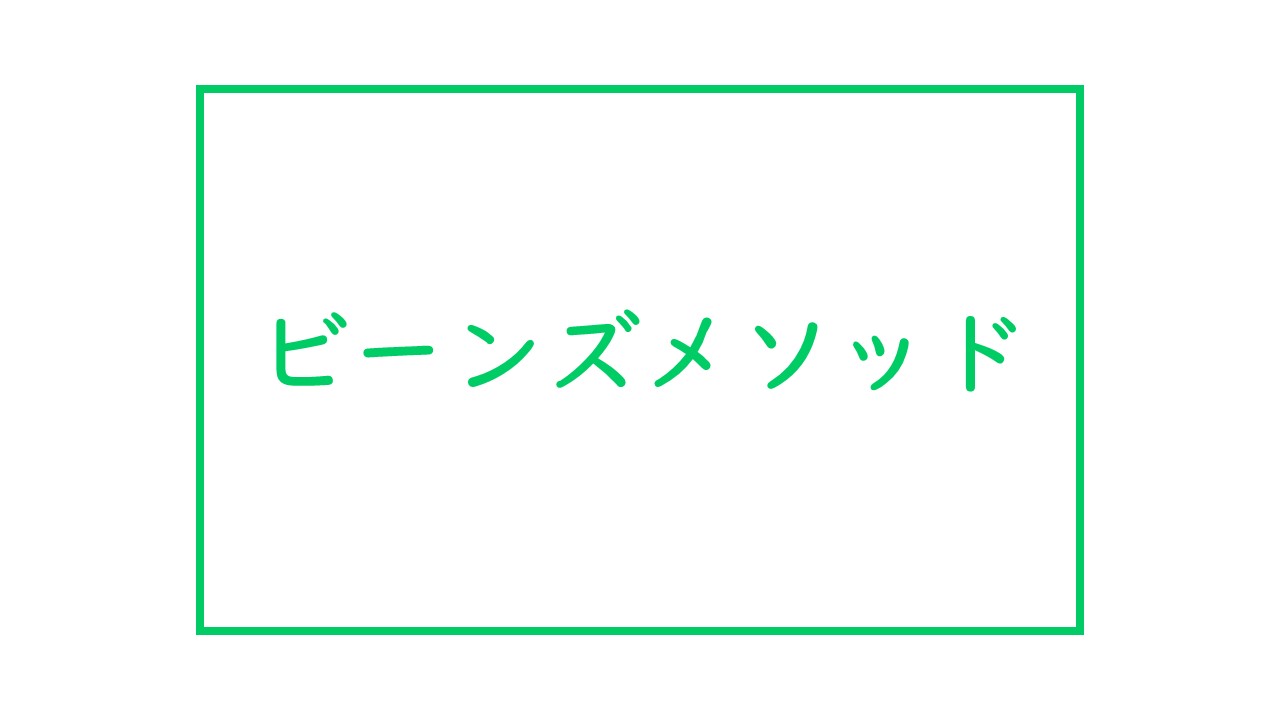
↓の動画では、大事なところだけをわかりやすく解説しているので、是非…!
さいごに(次回予告)
今回は、自己閉塞人──特にZ世代社員が抱える「道具的世界観」について掘り下げました。
この視点をもとにすれば、これまで「意味不明だった」彼らの言動に、一定の理解の道筋が見えてくるかもしれません。
次回(↓)は、この「道具的世界観」をベースに、自己閉塞人の行動パターンを4つのタイプに分類して紹介しています。
-──-Z世代社員のしんどさの根っことは?-300x157.jpg)
Z世代とどう向き合えばいいか、より具体的に見えてくると思いますので、どうぞお楽しみに。
また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、こちらの問い合わせフォームからお声がけくださいませ。
また、読者アンケートにも協力いただけますと幸いです!
(回答時間目安3分)








