こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。
前回の記事(👇)は、悩めるZ世代社員(に限らず全ての人)と向き合う際には「ままならなさを愛すべき課題として捉える」という信条が必要であるということを解説しました。
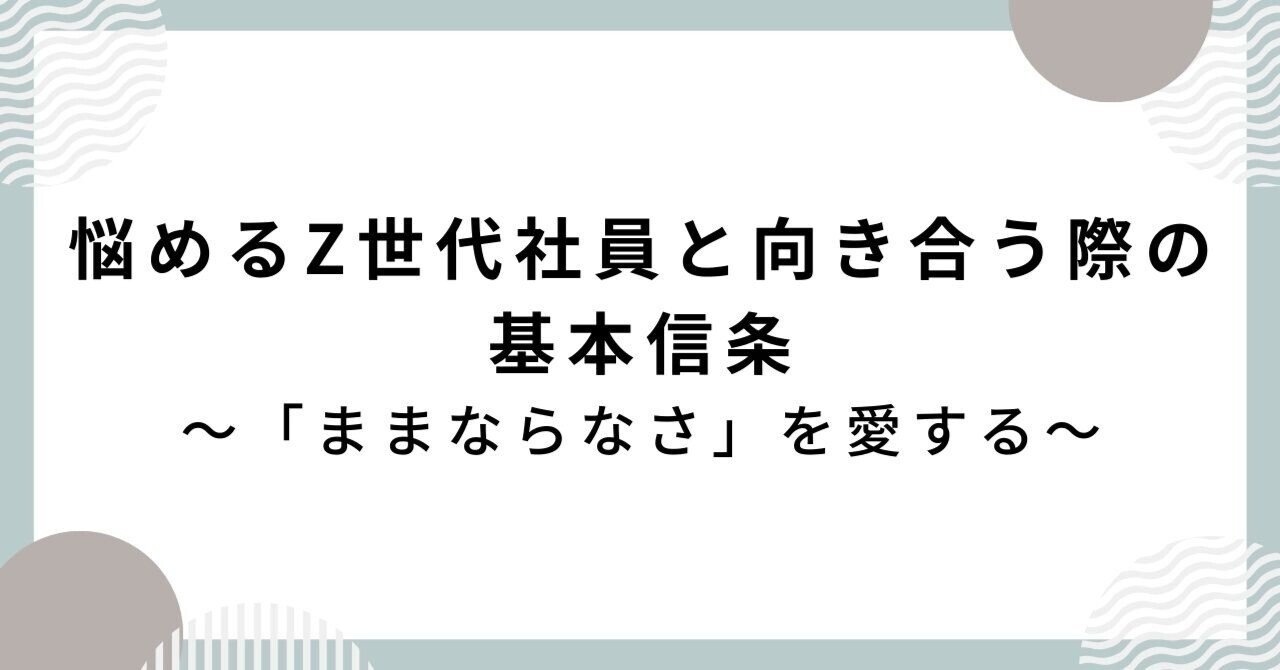
今回は、前回の記事でお伝えしたことを踏まえて、
「他者は他者である」という極めて当たり前の事実を再認識することの重要性
について解説していきます。
なお、今回の内容は、
これからリーダーになるZ世代社員向けの研修でお伝えしている内容を文字化したものをベースにしています。
Z世代社員向けの内容を元にしてはいますが、上司世代の皆様にとっても重要なメッセージであると思い、そのまま公開することにしました。
人間の根源的欲求と悪循環
人間には、2つの根源的欲求(※)があると考えています。
- 「他者から自分のことを理解され、愛されたい」という欲求
- 「自分の意思と自分のやりたいことを尊重してのびのび生きたい」という欲求
の2つです。
※「ビーンズメソッド」との違い
悩める10代のサポート方法をまとめたビーンズメソッドで定義している「ありのまま欲求」と「ドライブ欲求」とはレイヤーが違う概念ですが、一部重なることも意味しています。
一方で、この2つの欲求を実現するために、
人間は時として、「悪循環行動」をとってしまうことがあります。
悪循環行動とは、「自分が求めるものを得るための行動だが、その行動によって逆に自分の得たいものが遠のいてしまう行動」(※)のことです。
「悪循環とは、ある人が自分の置かれている状況を問題のあるものとみなし、これを解決しようとする行動に出るが、この解決行動自体がとうの問題を生み出してしまうというメカニズムを持ち、しかもこれが反復的に繰り返されるものを言う。」
長谷川正人『悪循環の現象学』ハーベスト社、p79
上記の2つの根源的欲求に対応する悪循環行動の代表例としては、
- 他者から理解され、愛されたいからこそ、自分のことを自分が求めるレベルで理解し、愛してくれない他者を過剰に攻撃したり遠ざけてしまったりする行動
⇒ 結果として、他者からの信頼を失い、自分を愛してくれる他者がいなくなる - 自分のやりたいことだけをのびのびやりたいからこそ、そんな環境を作ってくれない他者を過剰に攻撃してしまう行動
⇒ 結果として、他者からの信頼を失い、自分のやりたいことがやれなくなる
なお、これらの悪循環行動を私は「自己閉塞行動」として定義しています。
自己閉塞行動について詳しくは、👇のシリーズ記事をご覧ください。
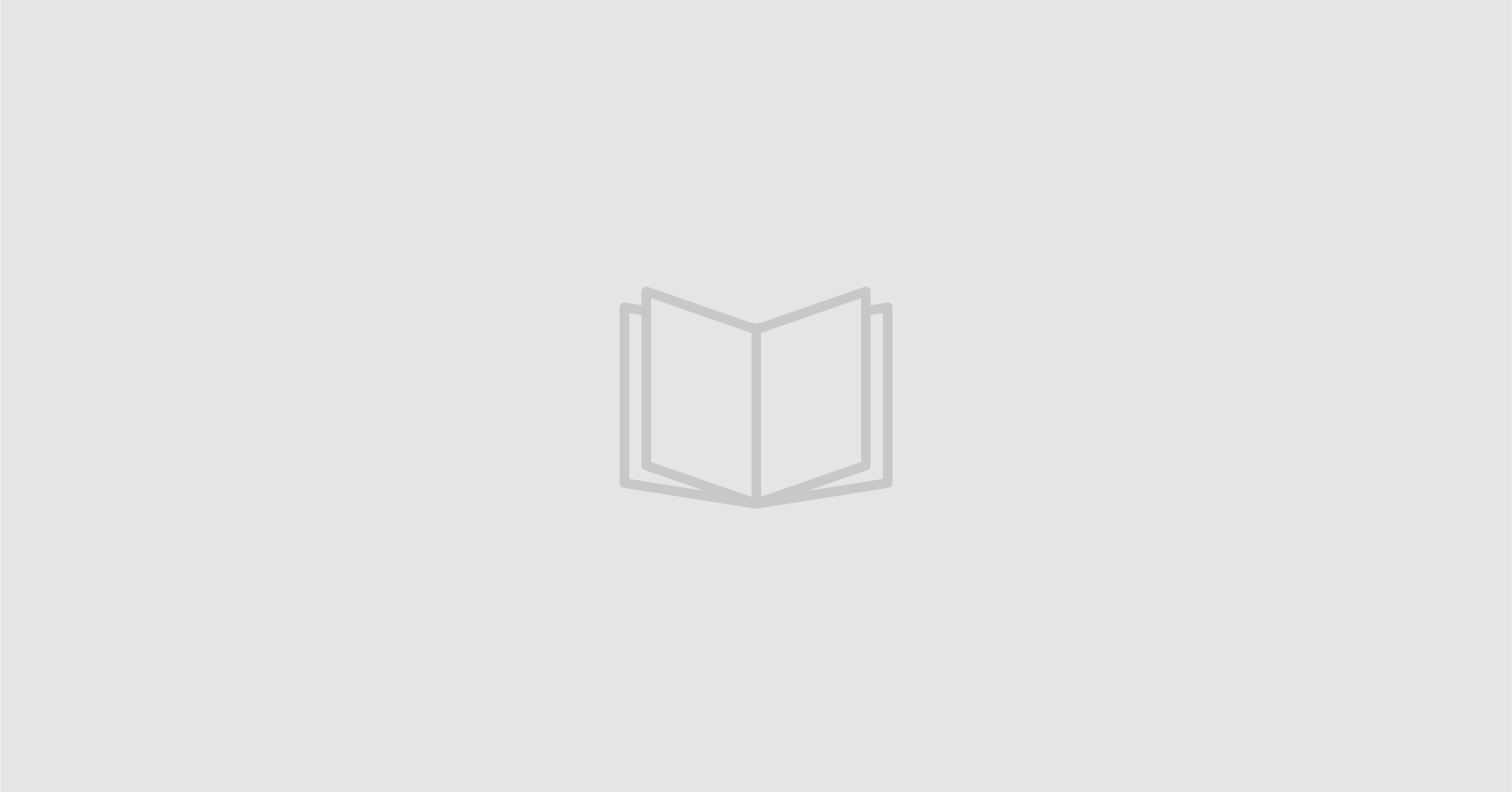
一方で、2つの根源的欲求を満たすことに対して矛盾した行動をとった方が、逆に2つの根源的欲求を満たしやすくなることが多いのです。
例えば…
- 他者に自分のことを理解し愛してくれることを求める前に、自分が他者を理解し愛する
⇒逆に、他者から理解され、愛される - 自分のやりたいことをちょっとだけ我慢して、他者との信頼関係構築を優先する
⇒逆に、他者から自分のやりたいことを応援される
ここまで説明した、
「2つの根源的欲求を満たす行動」
「2つの根源的欲求と逆行する”悪循環行動”」
を理解してもらえると、後述する内容が理解しやすくなるので、覚えていただければと思います。
他者の他者性
結論から言います。
他者は自分ではなく、他者です。
そして、他者も自分ではありません。
当たり前過ぎますね……
ただ、濃密な人間関係の中だと、この当たり前の事実が忘れられることがあります。
なお、他者が他者であることをかっこよく表現した言葉が「他者の他者性」(※)です。
※
これは筆者独自の概念ではありません。オープンダイアローグという統合失調症のケアのための技法・思想で提唱されている「他者には自分には理解しえない、他者性がある」という考え方の名称です。
そして、他者と関わるうえで、他者の他者性から導きだされる以下の2つの原則をよく理解する必要があります。
定理1:他者は思い通りに操作できない
他者は道具(👇)のように自分の思い通りに操作することはできません。
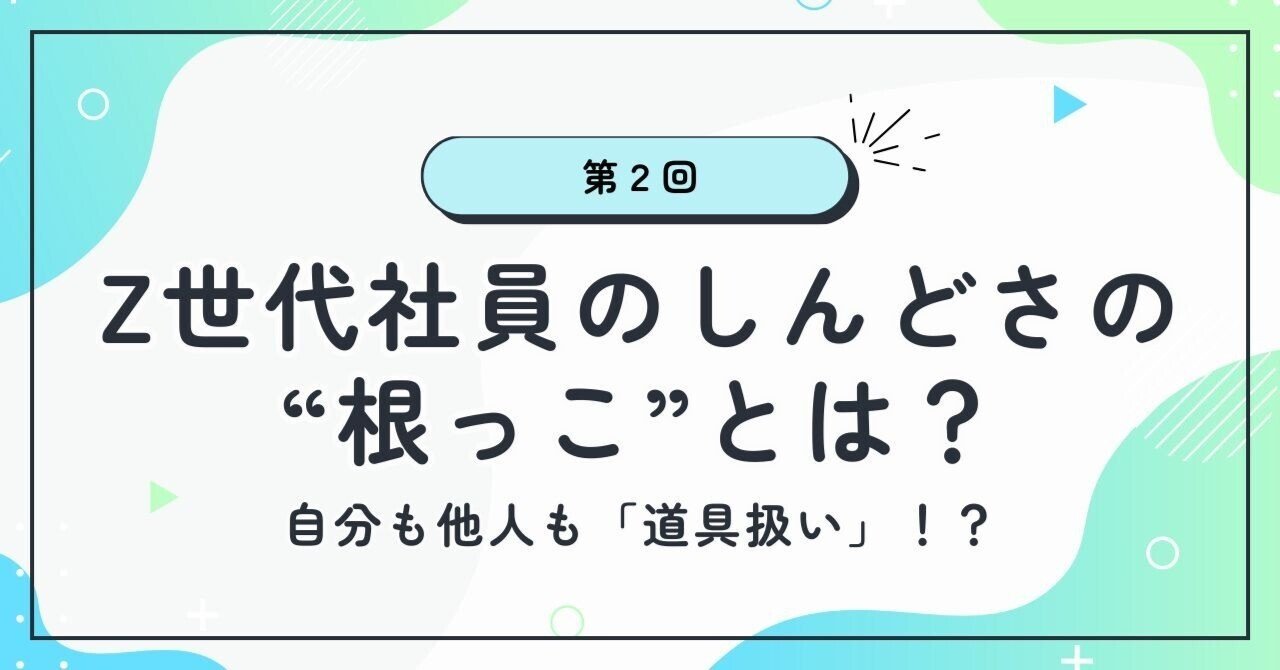
先述の通り、他者には他者性があるからです。
もし、完璧に操作することができるとしたら…
それは「人」ではなく「道具」です。
ただ、人間は先ほど述べた根源的欲求ゆえに、
「他者を自分の思い通りに操作したいし、できるはずだ」
という間違った考えに基づいた悪循環行動をとってしまうことがあります。
何度だって言いますが、他者を自分の思い通りに操作することはできません。
もちろん”操作”はできませんが、説得や依頼をすることはできます。
そして、その説得や依頼を精緻に丁寧におこなうことで、
相手がその説得や依頼を受け入れて、行動することもあります。(そういうコツも確かに存在します)
ただし、その説得やお願いに応じるかどうかは究極的には他者次第なのです。
根源的欲求と短期的には矛盾しますが、
ここはグッとこらえて、「相手に行動変容を求める前に自分がまず行動変容する」といったことが必要な場合も多いかもしれません。
そうなると…
「他者は自分の思い通りに操作できないなら、そもそも他者と関わりたくない」
「自分が思い通りに操作できる他者としか関わりたくない」
という人もいるかもしれません。
ただ、これはこれで冒頭に述べた根源的欲求と矛盾するので、逆にしんどくなってしまいます。
「操作」という関わり方は他者の他者性を無視しているのでうまくいかないですしね……
一方で、他者の他者性をふまえた他者との関わり方は、「お願い」「対話」「応援」などたくさんあります。
このワクチンを読んでいるあなたには、他者と関わり続けることは諦めないで欲しいのです。
定理2:他者は自分が見えないor見ていないものを見ている
人間は、
「自分から見えるものだけが真実であり、自分が見ていないものは存在しないもの」
と無意識に誤解してしまいがちです。
だからこそ、自分が見たもの・聞いたもの・経験したことだけを判断材料にして、他者に噴きあがってしまうこと(※)があります。
※
噴きあがり=他者にネガティブ感情をぶつけてしまうこと
当たり前ですが、他者は自分が見ていないものを見ており、経験していないことを経験しています。
また、自分から見えないものの代表例としては…
「他者の価値観」
「他者が考えていること」
「他者の現在の価値観や考え方の土台となっている、他者の過去」
があります。
他者に対して怒りという二次感情が大きくなった際は、
まずは、
「他者は自分が見ていないものを見て、経験していないことを経験している」
ということを思い出しましょう。
また、「他者には自分が見ていることが見えない」ということも深く理解する必要があります。
私たちは
「他者に自分の考えやつらさを察して欲しい・他者から歩み寄って欲しい」
と、(どうしても)思ってしまいます。
が、他者はエスパーではありません。
根本的には、他者は”私”を理解してくれないのです。
ですから、自分の考えや感情は自分から表明して、相手に伝えることが重要なのです。
「他者も自分が見ていることが見えている」という間違った認識を無意識に持ってしまうと、他者からすると意味がわからないタイミング・理由で噴きあがってしまうことになり、事態がより悪化します。
具体的には、
「え、そんなこと今さら言われても…」「じゃあ、もっと早く言ってよ……」
と相手(他者)を混乱させてしまうことになるのです。
もちろん、他者の側もあなたから話しかけられやすい雰囲気を醸し出すことに努力すべきでしょう。
ただ、私の記事はあくまで「自分(あなた)には何ができるか」というメッセージに絞っていますので、そこは了承いただければと思います。
とはいえ……
他者の他者性と、他者の他者性から導かれる2つの定理を頭では理解していても、
- チームの目標達成ために、他者を思い通りに操作したくなる
(操作できないと噴きあがる) - 自分から見えるものだけで他者を決めつけ、噴きあがってしまう
ということは頻繁に起きてしまいます…
これこそ、私たちが抱える大きな”ままならなさ”(👇)です。
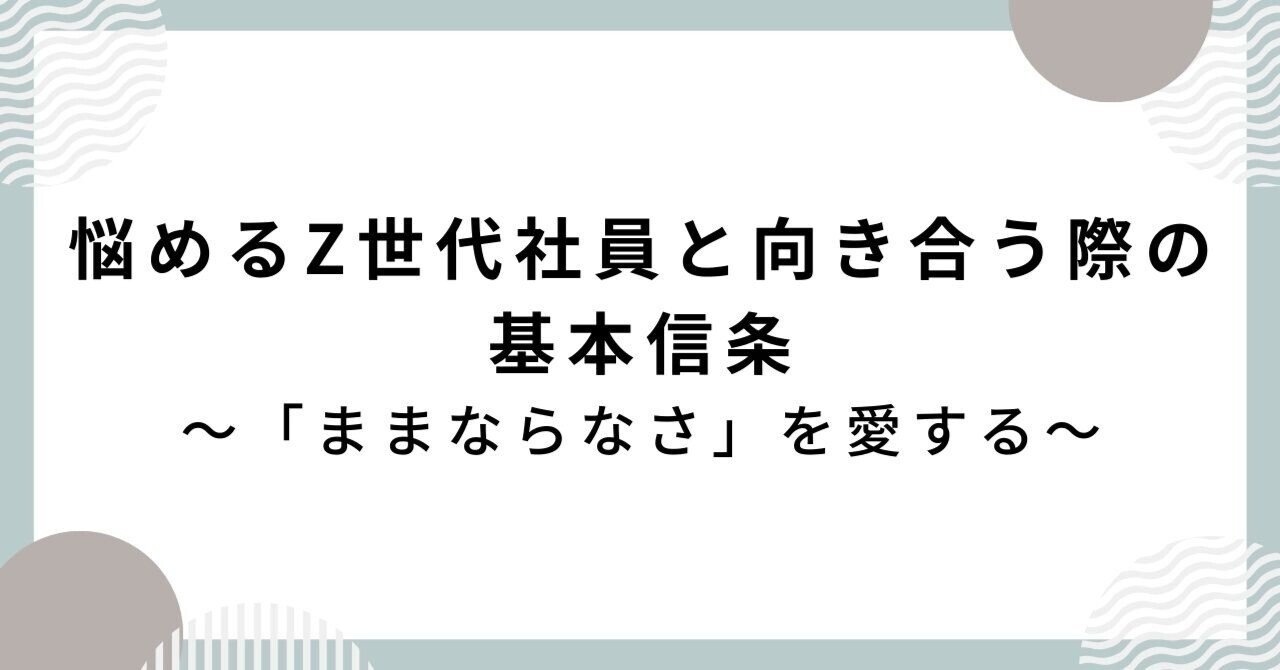
ただ、本ワクチンによってそのままならなさを明確にすることで、ままならなさが発動してしまう回数を少しでも減らせるように頑張ってもらえると嬉しいです。
もちろん私たちは聖人君子ではありません。
ですから、ままならなさの発動を完全になくすことはできません。
でもちょっとでも減らすことができたら、自分も他者も、もっと幸せに生きていけるはずです。
おわりに(次回予告)
ここまでお読みいただきありがとうございました!
これからお伝えする「Z世代社員に対するコミュニケーション手法や制度」は
前回お伝えした、
人のままならなさは愛すべき課題である
今回お伝えした
他者は他者である
という基本信条に基づいて実装される必要があります。
ここをご理解いただいたうえで、これからの記事も読んでいただければと思います。
次回は……
Z世代社員のパワーダウンに直結する「〇〇感」「△△感」「▢▢▢▢感」とは?
というテーマで記事を書いてみようと思います。
次回記事は👇
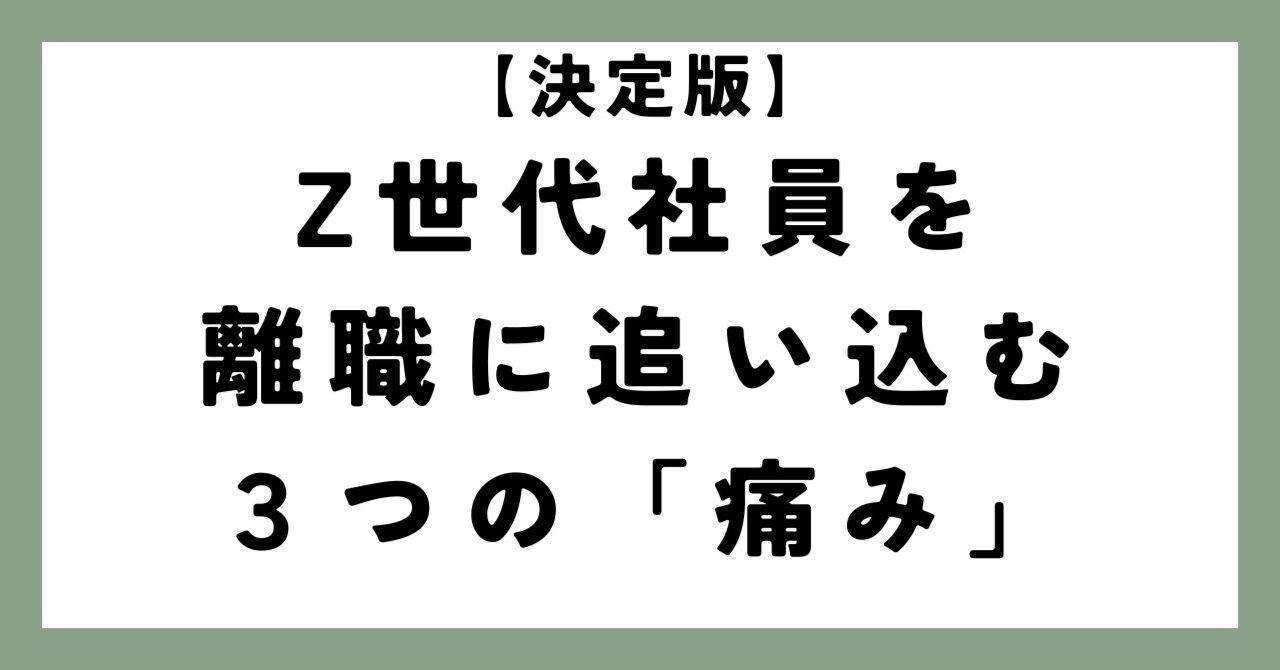
そして、次々回以降で具体的な予防法について紹介していきます。
是非お楽しみに!
また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、下記資料の下の問い合わせフォームから是非お声がけくださいませ。
また、読者アンケートにも協力いただけると幸いです!
(回答時間目安3分)










