はじめに
本編はコチラから
こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。
長澤啓(Nagasawa kei)
東京大学経済学部卒。1997年生まれ。
大企業・大企業の組合幹部向けの研修(ダイジェスト動画)・コンサルティングで、「Z世代社員の定着と活躍」のコツについてお伝えしている。長澤の取り組みについて詳しくはコチラ。
不登校支援専門塾である「学習支援塾ビーンズ」の塾長/副代表も務める。
今回はいつもとは趣向をガラリと変えて、「小説」です。
私が今まで見てきた令和の大学生の様々な実像を
「上成大学」という架空の大学に通う、「アユナ」という女子大生のストーリー
として短編小説としてまとめました。
まさか私が「小説」を書いてそれを世間様にお見せすることになるとは思いもよりませんでした……
(本は読むほうですが、文学には一切手をつけないですし……)
大変恥ずかしいですし、私にその手の才能がないのは重々承知しております。ただ、子ども・若者の実像を深く知っていただくためならなんでもやる覚悟ですので、小説の公開に踏み切りました!
「小説」という形式を選び、公開した理由
「え、小説!? なんで? 記事のネタが切れて迷走しだしたの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ネタは全く切れていませんし、迷走もしておりません。(笑)
今回、令和の大学生の実像を表現した小説を公開するに至った理由は以下の通りです。
本編はコチラから
メインの理由
これまで、独自理論をかなり抽象的に紹介してきました。(👇)
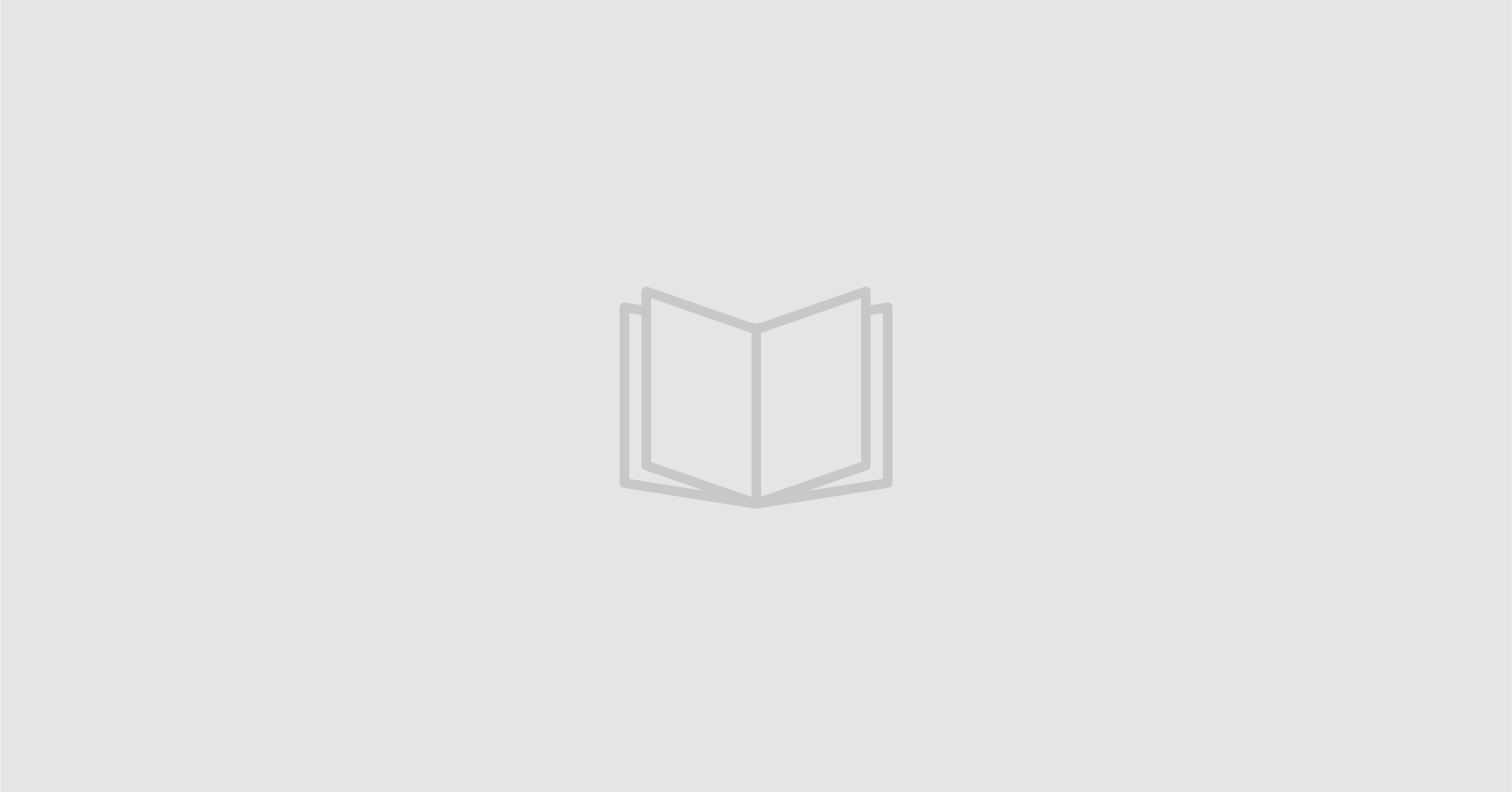
ただ……
一部の方から、
「内容に興味はあるが、抽象的すぎて理解しづらい」
「具体的な事例で説明してほしい」
というお声を頂戴してしまいました(笑)
私も、初習のものは抽象論よりも具体論から入ってもらった方が理解しやすいタイプなので、お気持ちは大変よく理解できます。
ただ、具体的な事例を羅列すると、それはそれで見づらいと思いましたので(分量も大変なことになりますし…)、短編小説という形を選択することにいたしました。
サブの理由
前回の記事でお願い差し上げた読者アンケート(※)の分析が終わるまでの場つなぎ企画として機能させたいからです。
※
既にご回答が届いており、大変うれしいです! ありがとうございます!
今手元にある現段階でのアンケート結果を見ても、やはりコアな読者の方から期待されているということをひしひしと感じました。
そんな皆様を長くお待たせするわけにはいかないと考えております。
小説をお読みになる前に必ずご理解いただきたいこと
その1
今回の小説のモデルは、私が今まで接してきた多くの大学生です。多くの大学生の様々な事例を「アユナ」という一人の女子大生のストーリーに織りこみました。
ですので、小説で紹介されている一つ一つのエピソードは全て実話に基づいています。
その2
今回の小説をご覧になると、「え、今の大学生って全員こうなの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、違います。
小説の主人公であるアユナは極端な事例です(極端とはいえ、本質的かつ典型的な事例ではありますが……)。
元気な大学生たちもたくさんいます。
詳しくは👇の記事をご参考ください。
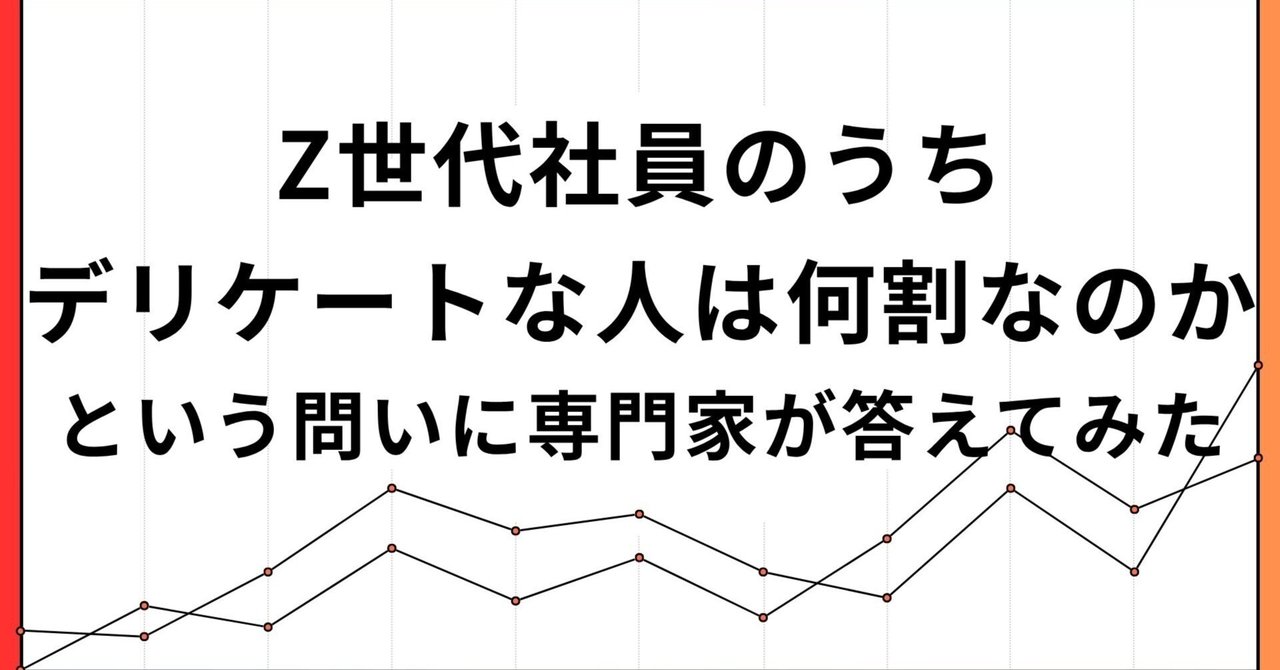
その3
主人公のアユナは「都内のそこそこ裕福で教育熱心な家庭」の出身の高学歴な人物です。
上記とは違う環境で生まれ育った令和の若者も多くいます。そんな若者はアユナとは少し違った心理構造・価値観を持っていると考えています。
ただ、根っこの部分ではアユナと同じような生きづらさ(👇)を抱えているのではないかと考えています。
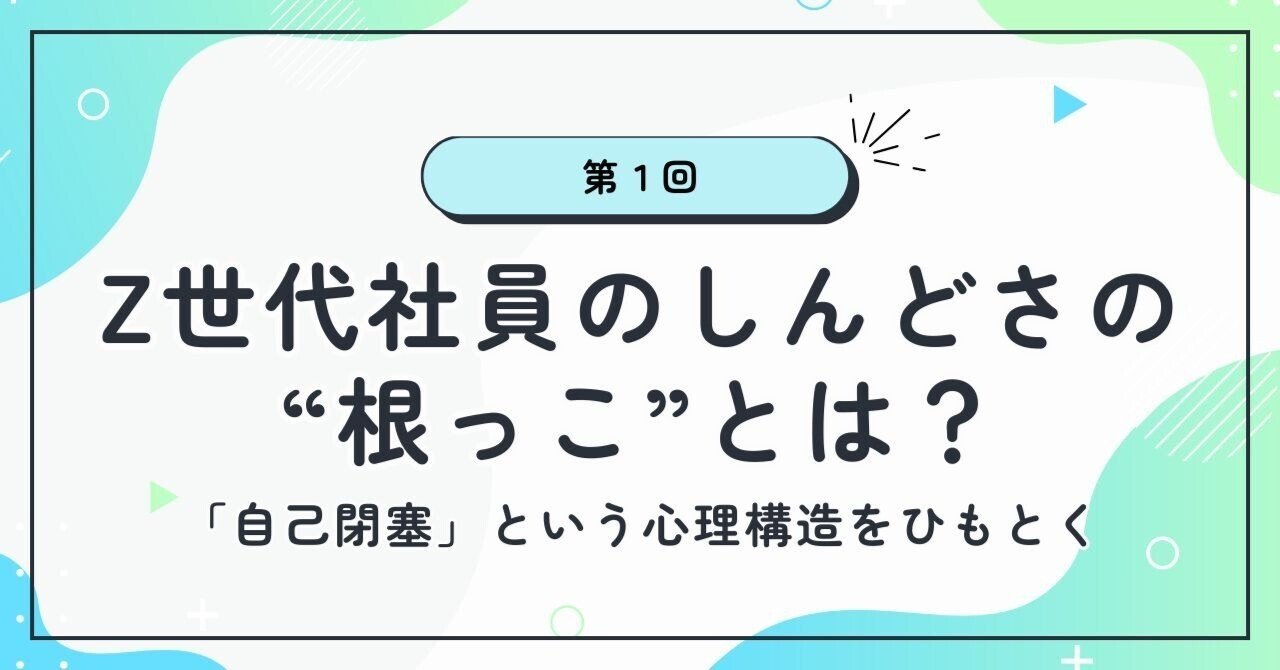
その4
「できれば…」なのですが……
この小説をお読みになった後に、👇の記事シリーズをご覧ください。
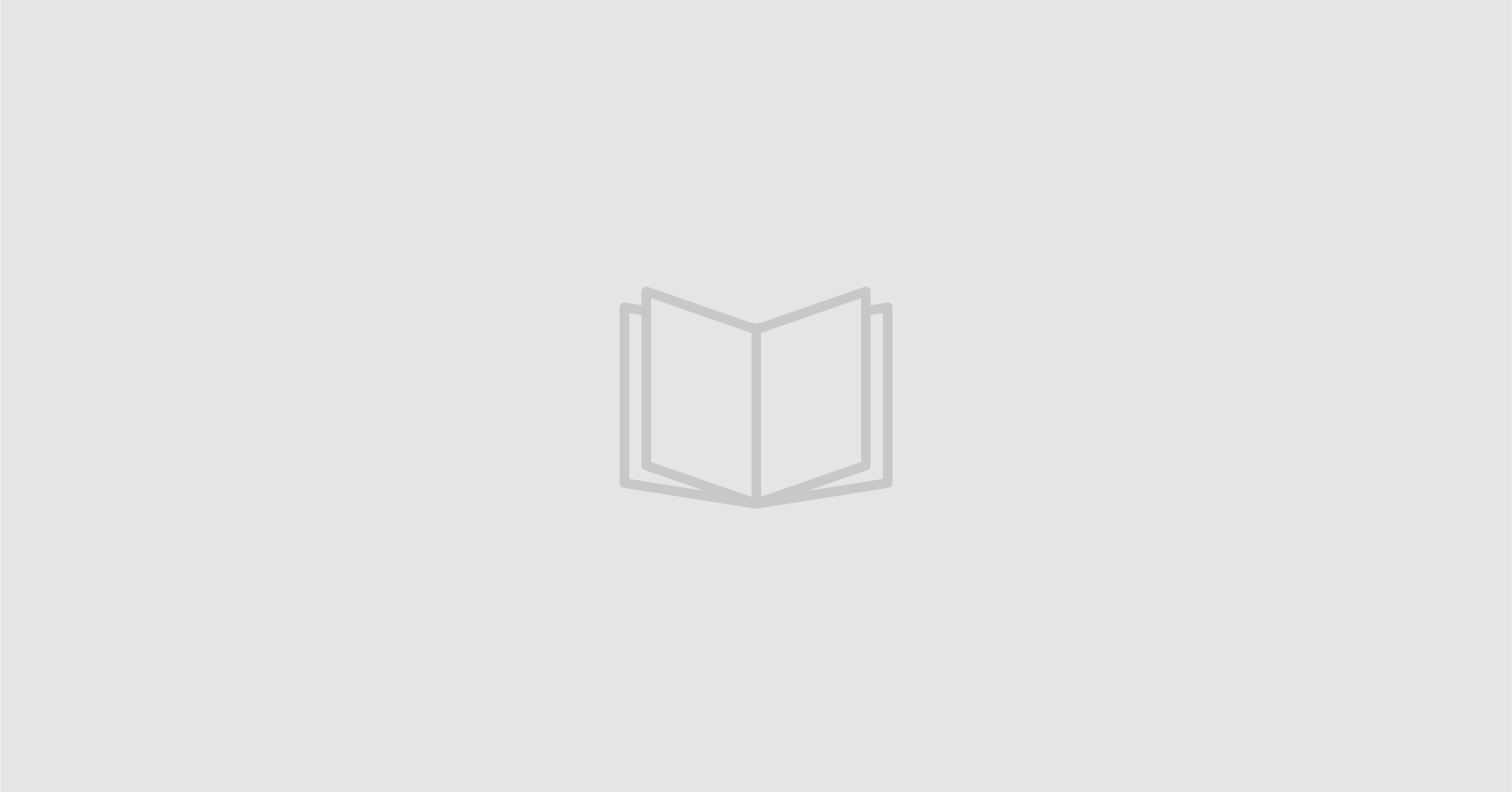
今回の小説で表現したZ世代の若者のしんどさの根っこやその原因について詳細に解説しております。
併せてお読みいただくことで、「小説で出てきたあのエピソードはこんな背景があったのか!!!」と深くご理解いただけると思います。
憧れと違和感のはじまり
大学3年生 晩秋
11月の初旬。随分と肌寒くなってきた夕暮れ時。
「おしゃれなキャンパスなんだけどなあ……」
大学2年生のアユナは、15秒に1回の頻度で鼻の奥を締め付けてくるイチョウの臭気に不快感を感じながら、足早に歩いている。
最近忙しくて寝不足なところに、この臭気が加わると、どうしてもイライラしてしまう。
文学部棟の角を左折すると、夕陽に照らされたレンガ造りの法学部棟のゴシック風アーケードが視界に飛び込んできた。
アユナは、3年半前の春を思い出し、反射的にうつむいた。
高校2年生 春
3年半前の5月。
ここ、上成大学は都心の閑静な文教地区に広大なキャンパスを構える。
ちょうどオープンキャンパスが開催されているところだ。
上成といえば、全国的にもそこそこ名の通った私立大学である。当然ながら、就活市場においてもかなりのブランド力を誇っている。
「都心にあるおしゃれな難関私立大学」ということで、全国の高校生たちの憧れの的にもなっている。
高校2年生のアユナは、緊張をほぐすために、お気に入りのKPOPを聞きながら、上成大学の門をくぐった。
実は、アユナは積極的な姿勢で上成のオープンキャンパスに来たわけではない。
オープンキャンパスにやってきた理由の一つが、通っている高校(そこそこ名の知れた中高一貫校)の担任の先生から、上成の受験を強く勧められたことだ。
「バトミントン部で頑張っている割には成績が良いじゃないか。上成くらい目指したらどうだい? まずは5月のオープンキャンパスに行ってきなさい」と担任。
「はい! 行ってきます!」と明るく返事するアユナ。
だが、心の中では、こうつぶやいていた。
「行きたくないな~…… てか、バトミントン部は別に頑張っているわけじゃないし…… サボってないだけだし…… でも、断るのも面倒だし、行くか。あ~、でも行きたくない……」
もう一つの理由は、同級生たちの存在だ。
「都内トップ」とまでは言えないまでも、名の知れた進学校であるアユナの学校の生徒たちは、
受かるかどうかは置いておいて、上成レベルの大学を目指すのが一般的だ。
アユナの中でも、「上成レベルの大学じゃないと同級生と比較して恥ずかしい……」という思いが自然と芽生えていた。
そして、なんといっても最大の理由は、母親を安心させるためだ。
アユナの母親は専業主婦。
昔は少し働いていたらしいが、大手製薬会社に勤めるアユナの父親と結婚してから、家事・2人の娘(アユナと5つ上の姉)の子育てに心と時間を割いてきた繊細で優しい女性だ。
アユナにとって、仕事一本で子どもたちに無関心な父親よりも母親の方がずっと大事な存在だ。
そして、母親を安心させたいのにはアユナの姉の影響があった。
大学4年生になったばかりの姉の就職を母親がとても心配していたのだ。
アユナの姉は、どちらかというと内向的な妹とは違ってお転婆で、
いわゆる「陽キャ」だった。
受験勉強には大して力を入れず、都内の中堅私立大に通い始めると、いわゆる「キラキラした大学生」としてキャンパスライフを謳歌しているようだった。
しかし、大学3年になった頃から、様子が変わり始めた。
「ウェブマーケティングのスタートアップでの長期インターン」に熱中しだしたのだ。
アユナにとって、「ウェブマーケティング」も「スタートアップ」も「長期インターン」もわけのわからない単語だった。
もちろん、それは母親にとっても同じだった。
「長期インターン」というわけのわからない活動に没頭する姉のことを母親は少しは心配していたようだが、大学の単位は(ギリギリとはいえ)ちゃんととっていたので、心の底では安心していた。
しかし、姉が「私、今の長期インターン先の会社に就職する!」と言い出してから雰囲気が一変する。
母親の顔からは笑顔が消え、「娘の決断を応援したいけど、そんな得体の知れない小さな会社になんか行って欲しくない……」という葛藤にゆがんだ表情になっていた。
「お母さんはなんだかんだでお姉ちゃんの決断に何も言わないと思う。でも、私はお母さんに心配をかけたくない。最低限でも、アユナは一流大学を目指しているという姿勢を見せなきゃ。」
アユナの心の中に、そんな決意が芽生えた瞬間だった。
人一倍、他人の気持ちに敏感なアユナだ。
中学受験の対策をしていた小学生時代、母親が自分の模試の成績に(熱心な教育ママではないにせよ)一喜一憂していたことを強く覚えていた。
「私が頑張らなきゃ、私にとって一番大事なお母さんが悲しんじゃう」という気持ちが高校生になった今でもアユナの心の底に強く残っていたのだ。
・・・・・・
「パパの出身校でもある上成に行けば、ママも安心するはず!」
と何度も心で復唱しつつ、イヤホンを外し、レトロな正門をくぐり、アユナはオープンキャンパスの受付に向かっていった。
オープンキャンパスの印象は上々だった。
上成といえば、おしゃれでちょっとはっちゃけたイメージがあったが、対応してくれるボランティアの大学生たちの雰囲気が落ち着いて見えたのだ。
(もちろん、ダサくない範囲で!)
大学生たちの落ち着いた髪色を見つめながら、「どちらかといえば陰キャの私でも、友達できそう……」とアユナは安心した。
そして、案内役の大学生に先導されたアユナたちの一行は、正門を出発し、法学部棟のアーケードまで来た。
大学正門と一直線上に並んでおり、「上成大学といえばこの場所」とも言える、有名なスポットで、アユナもパンフレットやHPで何度も目にしていた。
案内役の大学生が、アーケードの隅の方を指さしながら、限りなく棒読みに近い説明を、貼り付けたような笑顔とともにしてくれる。
「ここが黒ずんでいますよね。これは、50年以上前に起きた、がくせいうんどうでかえんびんが投げつけられた跡です。学生がこんなことをするって、今じゃ考えれないですよね。」
案内役の大学生と同じく、アユナにとって、「がくせいうんどう・かえんびん」なんてよくわからないし、そもそもどうでも良い。
そんなことより、レンガ造りの建物とアーケードの奥に見える、
イチョウのまばゆい緑を映し出すガラス張りの学生ホールのたたずまいに心惹かれた。
「古さ」にも「新しさ」にも振り切っていないおしゃれなキャンパス・極端なファッションやコミュニケーションスタイルではない「ちょうどいい感じ」な上成生の姿……
全てがアユナに安心感を与えた。
受験期
そこから、アユナは上成の社会学部を第一志望に据えて、受験勉強に邁進した。
「なんで社会学部なの?」
母に問われて、アユナはこう答えていた。
「私、弁護士になるわけじゃないし法律とかよくわからないし法学部はちょっとなあ……。文学部も本好きじゃないから無理だし……。でも、社会学部ってなんでも学べそうな感じがするから、ちょうどいいと思ってる。」
注)
実は筆者は大学受験のプロでもあるのですが(というか元々はそちらが本業)……
学際系・教養系の学部の人気が上昇しているように思います。逆に、法学部のような、かつて人気だった学部の人気に陰りが見えます。(参考となる事例)
なお、アユナの「法学部→弁護士」「文学部→本」という浅いイメージは偏差値が高い高校生の中でも割と珍しくない気がします……(笑)
これは昔からそうだったのかもしれませんが……
アユナは勉強には向いているタイプではあったが、好きでもなかった。
というか、むしろ嫌いだ。
中学受験時代にボロボロになりながら模試の順位上げていた軽いトラウマがあったからだ。
だから、一瞬は「総合型選抜」の受験も検討した。
ただ、「自分のやりたいこと」を熱心に教授たちにプレゼンするという入試形式であると知った瞬間、一般入試での受験を決めた。
高校の「探究」の時間で、仕方なくこじつけた「自分が興味があること」を、それっぽく「調べた」成果を(目立ちたくないのに)皆の前で発表させられたときの嫌な思い出がフラッシュバックしたし、勉強せずに大学に入るのはなんだか「ズル」な感じがしたからだ。
注)
一部の高校生・大学生の間に「推薦コンプレックス」「一般入試至上主義」が蔓延しているように思います。
※なお、ここでは総合型選抜も「推薦」にカテゴライズしています
高校生たちから「推薦はズル」「大学に入っても勉強についていけなくなる」と何度聞いたことか……
大学生たちから「私は一般じゃないので……」という謎のコンプレックスを何度聞いたことか……
ちなみに、推薦組と一般入試組で大学入学後の成績に大した差はないどころか、推薦組の方が成績が良いことを示唆するデータもあるようです。
(詳しくはコチラ)
母親は相変わらず姉のことを心配していたようだった。
いや、「ようだった」ではない。
感受性の強いアユナには、母親が姉を心配する気持ちが明確かつ詳細に理解できた。
母の浮かない顔を見るたびに、アユナの心は傷んだ。
そして、そんな母に寄り添おうとしない父の相変わらずの無関心さにも静かな悲しみと怒りを覚えた。
でも、その度に「私がお母さんを絶対に心配させない」という気持ちが強くなり、勉強に精を出すことができた。
そして、ご存じの通り、アユナは上成大学社会学部に合格する。
大学1年生
大学に入ったからといって、これと言って何かをしたいわけではなかったが、
「極端」に振れない範囲でキラキラしたキャンパスライフを送りたかった。
アユナはその願望を実現するために、無理をしない範囲で全力で「大学生活」にコミットした。
まず、中高時代に覚えた「誰も傷つけないけど、何も主張しない笑顔」にさらに磨きをかけた。
この「笑顔」を自分の表情のデフォルトに設定しておけば、そこそこ「友達」ができるし、何より嫌われることがない。
次に、自分のコミュニティ(居場所)を探した。
1年生の間よく顔を合わせるのは語学の授業のメンバーだが、「語学の授業」に新歓コンパも飲み会もあるわけがない。
ただ、自分から話しかけるのなんてもっての他なので、語学のクラスを自分の居場所にするのは諦めた。
(ちなみに、アユナが初対面の人たちへの自己紹介で必ず使うフレーズは「私は恥ずかしがりやなのですが、話すのは好きです。なので、是非私に話しかけてください」だ。)
あと、語学のクラスを避けた理由はもう一つある。
それは、「浅はかでノリが軽すぎる陽キャ」が幅を利かせているように見えたからだ。
アユナにとって、「バカ陽キャグループ」(アユナは彼らのことを心の中でそう呼んでいた)は最初見たときから、恐怖に近い嫌悪の対象だった。
特に、ピンクの髪色の声でひときわ声がデカく、いつも麻雀の話をしている「ピンクのアイツ」が嫌いだった……
アユナにとっては派手すぎるファッションもさることながら、コミュニケーションスタイルがどうしても受け入れられなかった。
いつもいつも大声で「あいつ、~~の家で飲んだくれて潰れたわ!」というアユナにとって想像の範囲外の「過剰な遊び」について話していた。
「高校時代にオープンキャンパスで見た上成生にはこんな奴らいなかったのに…… コイツら、上成に入学したのに、本当にバカ…… マジで無理。」
という思いが語学の授業のたびにアユナの心の中をグルグル回っていた。
というわけで、大学の中で自分のコミュニティとなり得るのは、サークルしかないように思えた。
しかし、「バカ陽キャグループ」が軽くトラウマなので、なるべく平和で大人しそうなサークルを探さなければいけない。かといって、ダサいのも嫌だ。
そこで探し当てたのが、KPOPダンスサークルのSNICK.だ。
熱狂的とまではいかなくてもKPOPはそこそこ好きだし、小さな頃はダンスも習っていたし、運動は得意な方だったからだ。
新歓で話した先輩たちがアユナと同じ「誰も傷つけないけど、何も主張しない笑顔」で話しかけてくれて、とりあえずの安心感を覚えたのだ。
とはいえ、結局はSNICK.もアユナにとってパーフェクトに居心地のよい安住の地とはならなかった。
そもそも、SNICK.は総勢150名を超える大所帯のダンスサークルだ。
そんなに人数が多ければ、アユナが何よりも嫌う、「バカ陽キャグループ」も中にはいるのだ……
飲み会では、「バカ陽キャグループ」の品のないコールが飛び交い、何人かが必ず潰れる。
アユナは嫌気が差し、サークルの飲み会には参加しないようにした。
悩んだが、夏合宿も参加しなかった。
案の定、サークルのLINEに投稿された夏合宿のアルバムには、「バカ陽キャグループ」の写真が何枚もアップされていた。
「行かなくてよかった……」
アユナはアルバムを見るなりそう思った。
ただ、認めたくなかったが、ある種のうらやましさも感じなくもなかった……
あと、アユナにとって小さな不快感になっていたのが、「容姿が良いとされる子」が露骨にモテることだ。
SNICK.の男子たちは、容姿が優れている子を露骨にちやほやする。
客観的に見て、アユナも「顔が可愛いタイプ」ではあったが、容姿への自己評価はかなり低かった。
そして、「自分よりも可愛い子」がより男子にちやほやされているのを見るたびに、男子への軽蔑の気持ちと自分の容姿への低い自己評価がより強固になっていた。
とはいえ、170人もメンバーがいるということは、アユナが傷つかずに済む小集団もあることにはあった。
「過剰な」飲み会もないし、とりあえずその集団の中にいる限り、アユナが傷つくことはなかった。
ただ、お互いが本当は何を思っているかどうかは分からなかった。
毎日の昼休み、SNICK.のいつものメンバーで食堂に集い、「誰も傷つけない話題」で時間を潰す。
放課後の予定が合えば、渋谷近辺に繰り出して、お気に入りのカフェで「誰も傷つけない話題」で時間を潰す。
(ただ、こんなことも1か月に1回あるかないかくらいだ)
入学当初に憧れた「キラキラキャンパスライフ」はとりあえず実現できたかもしれない。SNICK.のいつものメンバーも、気が合うといえば合う「良い友達」だ。
でも、アユナはたまにこう思った。
「私の本当の居場所はここじゃないかも」
何者かになりたくて
大学2年生 春
2年生になった。あのオープンキャンパスから、ちょうど2年が過ぎたことになる。
サークルでは、自分のコミュニティを確立・固定化させて、「バカな陽キャグループ」と必要以上に関わらずに済むようになった。
そして、アユナは随分と垢ぬけた。
無難なファッションに身をつつみ、お得意の「誰も傷つけないけど何も主張しない笑顔」で友達と接する。
相変わらず、学部には試験の際に協力できる友達がいないので、授業には毎回出席して自力で懸命にノートをとる。
良い成績ではないが、単位は全てとっている。
学外では、バイトも始めた。
高校時代に通っていた大手進学塾でのチューターの仕事だ。
楽しくはないが、お金はとりあえず稼げるので、悪くはない。
初めての彼氏も出来た。
SNICK.のメンバーで、何度かデートをして、「一緒にいても苦じゃないなー」と思っていたところ、彼の方から告白してきたのだ。
本当のところ、恋愛にそこまで興味はなかったが、振るのもかわいそうだし、何か波紋を呼ぶのも嫌だったので、付き合うことにした。
「燃えるような恋」では全くないが、「彼氏」も案外悪いものではない。
ただ、この頃のアユナには「バカな陽キャグループ」以外の、苦手な人たちが生まれていた。
それは、「何者か」になれている人たち。
上成大学は難関大学だ。
全国から、地頭が良くて行動力がある学生が集まってくる。
1年生の間は目立たなかったそんな彼らの存在感が2年生になると徐々に強くなり、アユナの視界にも入るようになってきた。
1年生の春休みの終盤、アユナがいつも一緒にいたメンバーの一人がSNICK.を辞めた。
SNICK.での活動ではいつも一緒にいて、昼休みの食堂で「誰も傷つけない話題」に花を咲かせていた子だった。
聞くところによると、海外大学の学生と政治・環境・文化などについてディスカッションをする国際交流サークルでの活動をより注力したいのが理由だったとのことだ。
なんでも、サークルの幹部として、中国の浄華大学とアメリカのアイビー大学の学生とのディスカッションイベントに大学生活の全てを賭けたいのだそうだ……
アユナにとって、小さな晴天の霹靂だった。
その子がそこまで国際交流に熱い想いを持っていたとは知らなかったのだ。
国際交流サークルをかけもちしているのはもちろん把握していたが、「英語がちょっとしゃべれるようになりたい」くらいのモチベーションだと勝手に思っていた。
そもそも、本人とは当たり障りのない雑談しかしたことがないので、知らなくて当然なのだが……
その子が国際交流サークルでの活動に注力するためにSNICK.を辞めたと知ったとき、アユナは自分の奥底から「とてつもない焦り」が湧いてくるのを感じた。
アユナには、中高時代から一貫して、「やりたいこと」などない。
しかし、1年生の頃から、先輩たちが就活に挑んでいるのは視界の中に入っていた。
先輩たちの「○○ちゃん、~~に内定もらったらしいよ!」「△△くんは商社の最終面接まで行ったんだって!」といった噂話を聞いて、就職先企業のなんとなくの格付けも少しずつ理解でき始めてきた。
問題は、就活においては「ガクチカ」なるものが必要らしいということだ。そして、数ある会社の中から、「自分のやりたいことができる会社」を見つけなければいけない……
注)
ガクチカ:「学生時代、力を入れたこと」の略。代表的な就活用語。
そして、3年生の夏には就活の前哨戦であるサマーインターンが始まる。
3年の夏までに、最低限のガクチカを手に入れなければならない。
行きたい業界・企業の方向性も決めなければいけない。
アユナに、中学受験時代・中高時代の記憶が蘇る。
なんとしても、序列が上位のところに行かないといけない……
上成生として恥ずかしくない企業になんとしても就職しなければならない。
ただ、やりたいことはない。
このとき、先輩たちの就活体験談を少しだけ聞きかじったアユナがぼんやりと考えていた理想の就職先企業および職場は以下のようなものだった。
- 大前提として、上成出身者の就職先として恥ずかしくない大企業
- 大前提として、上成出身者として恥ずかしくない給与水準
- 働き方(対面/オンライン)を自分で選べる
- 働く時間も融通が効く(フレックス)
- 自分は大きな責任をとらなくても良い。(営業)成績の責任もとらなくてよい
- ハードワークはないので、有休もしっかりとれて、自分のプライベートも楽しめる(もっとも、アユナに熱中できる趣味などはなかったが…)
- 怖い上司や先輩がおらず、厳しいノルマやタスクの期限はない
- 他の社員との露骨な競争はなく、平和にのんびり仕事ができ
- 職場の人間関係は平和で自分が攻撃されることはないし、誰かが攻撃されているのを見ることもない
- 自分がやるべきタスクが明確で、かつタスク内容について完璧なマニュアルがあり、仮に失敗しても自分への評価は下がらない
- (マスト条件ではないかもだけど)自分の個性を活かして、クリエイティブなことがやれる
- (マスト条件ではないかもだけど)自分の貢献で目に見える誰かが幸せになっている
すぐに自分と他人と比べる割に「競争」が嫌いで、猛烈に何かに打ち込むことにも忌避感があり、何よりも、失敗することや人から嫌われることを何よりも嫌がるアユナにとって、「会社選びの軸」はどうしても以上のようなものにしかならなかった。
しかし、アユナは決して楽ではない受験戦争を勝ち抜いてきただけの、最低限の行動力と地頭はある。
自分が「何者かになるための、ここではないどこか」を求めて、動き始めた。
まず、目をつけたのが、
・プログラミング
・ライティング
などのスキルを身につけることだった。
上成にもこれらで、そこそこの成果を出している人がいるということをなんとなく知っていたからだ。
ただ、根っからの文系を自認しているアユナにとってプログラミングはどうしても気持ちが動かない。
ライティングも、「自分が書いたものが世に出る」というのは自信がないアユナにとって少し荷が重すぎる。
他にも、「留学」なども考えたが、アユナにとってあまりにコストが大きすぎたし、そもそも海外に興味はない。
そこで思いついたのが、「長期インターン」だ。
そう、アユナの姉もやっていたアレだ。
高校生の頃は分からなかったが、当時の姉のような大学生が今目の前にいたら、アユナにとって眩しく感じただろう。アユナ自身もそのことを痛感していた。
長期インターン……
姉もやっていたし、時給も発生することが多いし、「社長直下」「新規事業立ち上げ」などいかにも何者かになれそうなスキルや経験を得られそうな感じが満載。
そう、アユナにとって、「長期インターン」は低コストで何者かになれそうなベストな選択だったのだ。
・・・・・・
そうと決まれば、早い。
長期インターン専門の求人サイトで、自分に合った企業を探し、すぐに面接を受けた。
結果は採用。
お得意の「誰も傷つけないけど何も主張しない笑顔」を発動させ、大人が喜びそうな主体性アピールをすれば、いっちょあがりだ。
「なんだ、いけるじゃん」
アユナは採用された瞬間に「何者か」になれた気がし始めた。
アユナが参加した長期インターンでは、「スタートアップで、社長直下の新規事業立ち上げ」ができると謳っていた。
期待に胸をふくらませて、活動初日……
集まっていたのは、上成を含め、名門大学の学生たち数名。
基本的な研修を受けたあと、外コン出身(これもアユナが惹かれたポイントだった)という振る舞い・話し方、全てが洗練された社長から、長期インターンの目玉となる新規事業立ち上げについて説明を受けた。
やはり、「何者か」になれそうな期待感が強くなりつつも、アユナには早くも不安が募りだした。
周りのインターン生が、自分よりもずっと賢く有能に見えてしまったのだ。実際にインターン生との会議が始まると、その不安は確信に変わった。
「この子、私よりも賢そう……」
と不安になってしまうと、もう話についていけない。
実際はmtgの内容よりも自分の不安に気をとられていたがゆえに、話についていけていないだけなのだが、アユナの中では違った。
アユナにとっては、
「私が地頭が悪くて、ロジカルシンキングが出来ないからだ……」
としか考えられなかった。
帰り道、アユナはどうしようもない劣等感にさいなまれた。
・・・・・・
アユナが長期インターンを始めて、1ヶ月が過ぎた。
他のインターン生への劣等感はぬぐえていないどころか悪化していた。
このままでは、マズい。
周りのインターン生たちへの劣等感が渦巻く中で、アユナの中で強い渇きが生まれていた。
それは、「自分よりも立場も年齢も実力も上の誰かに自分を認めてもらいたい・肯定してもらいたい」という渇きだった。
アユナにとって、他のインターン生たちは「仲間」ではない。比較対象だ。
また、「自分の無能さがバレてしまうと、他のインターン生たちからバカにされチームから排斥されるかもしれない……」という恐怖も生まれていた。
この地獄を救い出してくれるのは、例の「外コン出身」の社長しかいないように見えたのだ。
そもそも他のインターン生たちと自分を比較し、評価するのは社長だ。社長にさえ認めてもらえれば自分の劣等性は解消されるように思えた。
ただ、その理屈で言えば、アユナの劣等性をさらに証明してしまう可能性があるのも社長だ。
だから、アユナにとって社長は恐怖の対象でもあった。
「自分だけを肯定してくれる社長」なのか「自分の能力のなさを証明してくる社長」なのか……
これが明らかになるタイミングは意外と早くやってきた。
アユナがまとめた提案を社長にプレゼンする日がやってきたのだ。
この日のために、アユナは全力を尽くしてきた。
なんなら、寝る間を惜しんで準備してきた。
もちろん、他のインターン生たちに相談してしまうと、自分の無能さがバレるかもしれないと思ったから、たった一人で頑張った。
そして、運命のプレゼン本番。
終わった瞬間、「我ながらよくやった……」と思った。
ただ、残念ながら、社長からのフィードバックはアユナの期待に反するものだった。
言われた内容はこうだ。
「うん。ありがと。まずターゲットの設定なんだけど、これが根本的にミスっているね。これは売上不足ゆえに停止されたプロダクトのリニューアル案だよね? これだと、過去と同じターゲット設定で同じような内容だから、良くても過去と同じ売上しか期待できないよね。やるなら、新たにどのセグメントの顧客を追加設定するのかということを決めないといけないよね。たとえばなんだけど……」
頼みの社長から自分の提案が否定された。
この事実のみが、アユナの心を打ち砕いた。
よく聞いてみると、社長のフィードバックは、全て的を射ているし、アユナの人格を否定しているわけでもない。
それどころか、アユナの今後の成長を願った愛のあるフィードバックもあった。
ただ、アユナにはそれが分からなかった。
社長が自分が一生懸命作った提案を肯定してくれていないということが分かった瞬間、意識が遠のいていった。
それからほどなく、アユナはこの長期インターンを辞めた。
社長にはインターンを辞めることのみを簡単に伝えるメールを送り、返信は見えないような設定にした。
さらに、長期インターン内で使っていたチャットアプリはアンインストールした。
ひび割れた笑顔
1社目の長期インターンを辞めたあと、
アユナの「誰も傷つけないけど何も主張しない笑顔」は、
「自分のしんどさと余裕のなさを巧妙に隠すための貼り付けたような笑顔」に変化していた。
しかし、アユナの中で、「何者かにならねば」という焦りは一切消えていなかった。
というか、むしろ強化されていた。
だからこそ、アユナはあらゆる長期インターンに参加し始めた。
2社目は営業系の長期インターンだった。ただ、「長期インターン」とは名ばかりで、営業担当社員の補助業務(という名の雑用)がメインだった。
簡単な補助だからこそ、やることが明確で、失敗することもなく、自分が考えたものに対して大人がネガティブなフィードバックをすることもなかった。
しかし、「何者か」になれた気は全くしなかった。だからこそ焦りが募り、新たな長期インターン先を探し始めた。
なお、2社目の長期インターン・サークル・塾でのチューターバイトは全て継続していた。
アユナにとって、一度入った組織から抜けることは、本当に心が痛み、ストレスがかかることだったからだ。
だから、しんどくても全ての活動を継続することが、短期的には合理的だったのである。
長期的には「ただ疲れるだけで何の実績も達成感ももたらさないだけ」であったとしても……
アユナが盲目的に様々な活動をかけもちしていたのにはもう一つ理由がある。
「空白のスケジュール」への恐怖だ。
何も予定がない1日があると、「何もしていない自分」への罪悪感・焦りがアユナの心を締め上げて、生きた心地がしない。
逆に、スケジュール帳が予定で埋まっていると、自分が「何者か」に近い存在になれた気になって、心が満たされるのである。
もちろん、心身は追い込まれるのだが……
さて、3社目の長期インターンに話を戻そう。
3社目は1社目とは違ってインターン生への教育制度が充実しており、2社目とは違ってインターン生の自由な挑戦の場が準備されていた。
アユナも「ここなら何者かになれる」と意気込んだ。ただ、ここでも、他のインターン生への苦手意識は変わらなかった。
ただ、この会社はインターン生への教育・フォローに力を入れていたので、インターン生の教育担当の社員がアユナの苦しさを見逃すことはなかったことが救いだった。
アユナは社員との面談に呼ばれ、優しく、現在のしんどい状況をヒアリングされた。
アユナにとっては、本当に久しぶりに大人から肯定され、心を抱きしめられた瞬間だった。自然と涙がこぼれた。
今まで誰にも話したことがなかったことを何時間にもわたって打ち明けた。
- 色んな組織に参加しているけど、その全てに熱中できていないこと
- 自分がどうしても嫌いな人たちのこと
- 1社目の長期インターンで辛い思いをしたこと
- 母や姉のこと……
全てを話した。
ここ数年で久しぶりに、心が満たされた気がした。
社員に自分の恥ずかしい部分まで知られたのが気まずくて、次に会うのがかなり億劫になりはしたが……
それから毎週、その社員に時間をとってもらい、あらゆる悩みを聞いてもらった。アユナの表情も日に日に明るくなってきた。
だが、そんな幸せも長くは続かなかった。
ある日、アユナは突如として信頼していた社員から「正論」を突き付けられたのだ。
「正論」とは、以下のようなものだ。
- アユナは、色んなチームに参加し過ぎているがゆえに、全てのチームでコミットが浅くなっており、であるがゆえに、このままでは充実した経験を得られない
- アユナは、他のインターン生(大学生)への苦手意識と比較意識が強すぎて、仲間をつくれていない
- 仲間を作れなかったら、心が満たされないばかりか、やはり充実した経験を得られない
アユナにとって、雷が落ちたような衝撃だった。
正論を言われた後、呆然自失状態で帰宅した。
帰宅した後、しばらくは、「社員の言っていることも一理あるな」と受け止めようとはした。
しかし、ベッドに入ってから、正論を伝えてきた社員への猛烈な怒りがこみあげてきた。
社員がちょっと感情的になった際に出たちょっとした口調や単語は、自分への攻撃・ハラスメントに感じられた。
現在の自分の状況がマズいということや自分のしんどさへの指摘が「決めつけ」の侮辱のように感じられた。
あまりの怒りにその夜は眠れなかった。
人から好かれることよりも嫌われないことを優先してきたアユナがここまでの怒りを感じるのは初めてのことだった。
翌日になっても怒りは収まらなかった。
この怒りをどうしても正論を伝えて来た社員にぶつけたかった。
しかし、本人に伝える勇気はなかった。
だから、その社員の上司に、長文のメッセージを送った。
上司なら、自分に代わって、その社員を叱り、自分にとって居心地のよい場所を復元してくれると思ったのだ。
もちろん、上司からの返信はつれないものだった。
そもそも社員が伝えてきた正論は筋が通っていたし、一部感情的なものもあったがハラスメントからはほど遠いものだったからだ。
返信にはそのことが理路整然とつづられていた。
アユナは絶望とともに、その会社での長期インターンを辞めた。
今度は連絡もなく。
再び、大学3年生 晩秋
法学部棟のゴシック風アーケードを抜けて、アユナは学生ホールに足早に向かっていた。
SNICK.の幹部会議まで時間がないのだ。アユナはSNICK.で、会計リーダーを務めている。
もちろん、やりたい仕事ではなかった。
ただ、断る勇気がなく、引き受けて今も惰性で続けている。
幹部会議では、自分が大嫌いな「バカ陽キャ」のサークルリーダーと話さなければいけない。
あまりの気の重さに、ガラス張りの学生ホールに映るイチョウの木々が色あせて見えた。
あの長期インターンを辞めてから色んなことがあった。
いや、ほぼ同じことの繰り返しだ。
2社目の長期インターンは、自分のちょっとしたミスが気まずくなってバッくれた。深くつながる仲間が出来かけた活動もあったが、自分が迷惑をかけているのではないかという疑心暗鬼にとらわれ、いたたまれなくなって突然辞めた。
大人からの承認を求めて、起業家などの「すごい大人」が集う名刺交換パーティーにも行ってみたが、成果は得られなかった。「自分のしんどさと余裕のなさを巧妙に隠すための貼り付けたような笑顔」は、もはや「自分のしんどさと余裕のなさを巧妙に隠しているつもりだけど周りにはバレバレなひきつった笑顔」になっていたから大人と会ったところでかわいがられないのだ。
サマーインターンはもちろん全敗した。SNICK.には外コンに内定が決まったメンバーもいた。だからこそ、唯一続けられているSNICK.で自分の進路の悩みを打ち明けることはできなかった。バカにされると思ったからだ。大学2年から付き合っている彼氏とはまだ続いている。ただし、彼氏の方がアユナよりも精神的に追い詰められており、ややアユナに依存気味になっていた。昨日も、夜遅くまで彼氏との長電話の後、就活用の自己分析をしていたために、寝不足になっている。
「私の長所は協調性と傾聴力があって、人に優しいところだからな……」 彼氏との関係を解消できない理由と自己分析の成果を無理やり結びつけて、自分を納得させる。
……うつむきながら、そんなことをボーっと考えていたら、視界の端をピンク色の何かが過ぎ去っていった。
11月の上成のキャンパスではなかなか見ない色だ。ぎょっとして振り返ると、自転車を押しながら、興奮気味に友人と話すピンクの髪色の見覚えのある横顔があった。
「あれは……」
大学1年時の語学のクラス。アユナが何よりも嫌っていたピンクのアイツだった。
「もう俺さ、休学して映像制作に本気だしてみるわ! クライアントから案件もらえるようになったし、ここで勝負かけたいんだよね!」と、ピンクのアイツ。
正門の向こうの夕陽が照らすその横顔がアユナには絶望的に眩しく見えた。
~おわり~
おわりに
アユナの物語をここまでお読みいただきありがとうございました!
私も書きながら、「自分も結構、アユナに似ているところかあるな~……」とちょっと心がえぐられていました(笑)
3年生の途中までのアユナを上司世代の皆さんが見たら、多くの方が
「とても活動的で、いい子じゃん! なんだかんだでZ世代も頑張ってるじゃん! 日本の未来は明るい!」
と思ってしまうことでしょう。
ただ、小説をご覧いただくとわかるように、ぱっと見はいい子で活動的な若者も実は心の奥底でしんどさを抱えていることが多いです……
だから、ちょっとしたことで傷つき、パワーダウンしてしまう……
このことをアユナの物語を通じて、上司世代の皆さんにお伝えできれば幸いです。
また、👇のシリーズ記事も併せてお読みいただくと、アユナの思いの背景にある構造について理解が深まります。是非ご覧ください!
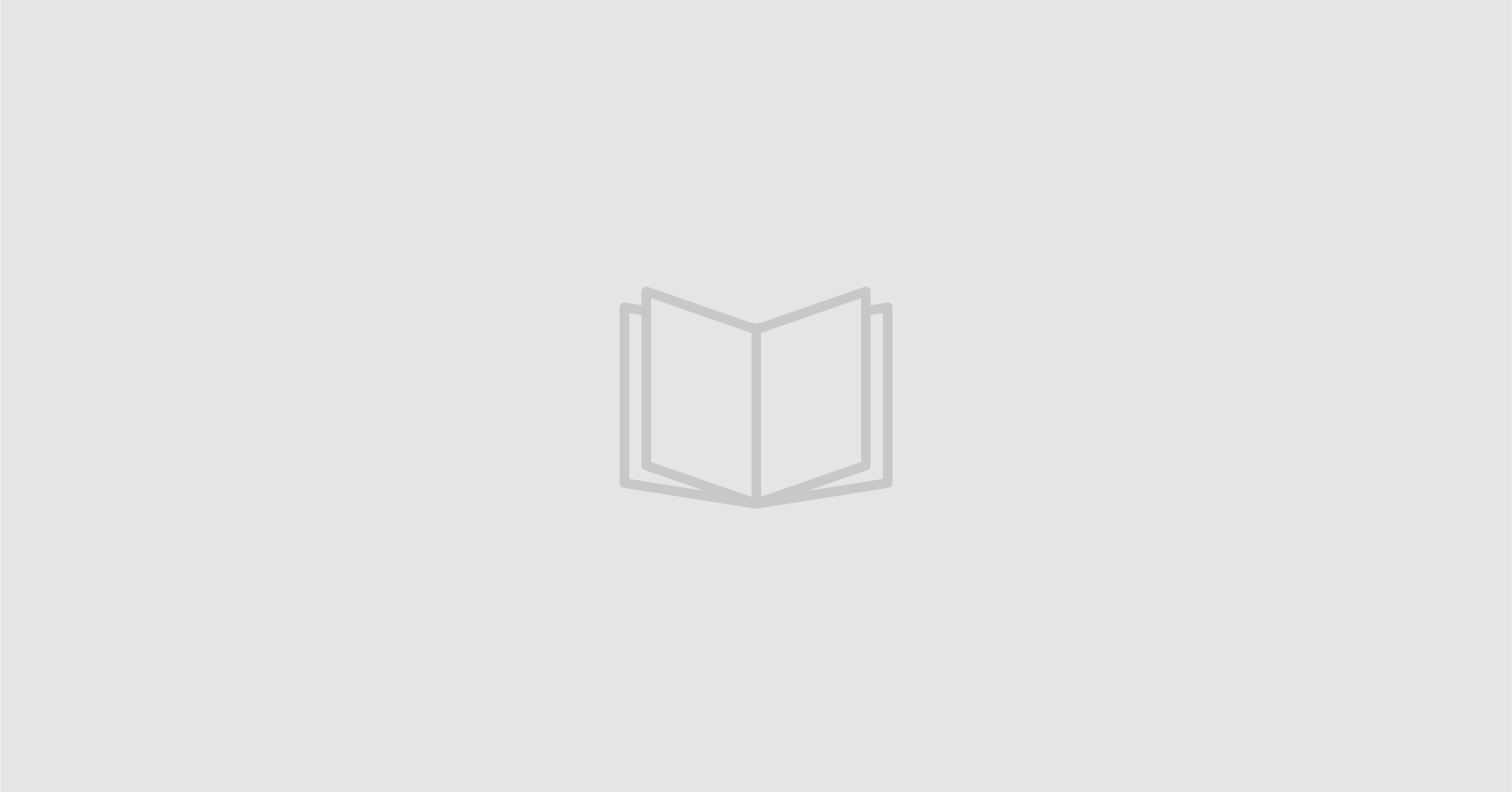
さて……
前編でもお伝えしましたが、
まさか「自作の小説をネットで公開する」ことになるとは思ってもいませんでした……
過去の私が知ったら、卒倒してしまうかもしれません(笑)
私のこうしたネガティブ感情を成仏させるためにも、是非以下の読者アンケートにご協力いただけますと幸いです!
(既に多くの方にご回答いただいておりますが、もう少しだけ皆様のお声が必要です!)
また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、本記事最下部の問い合わせフォームから是非お声がけくださいませ。












